|
�@�@�@�@
|
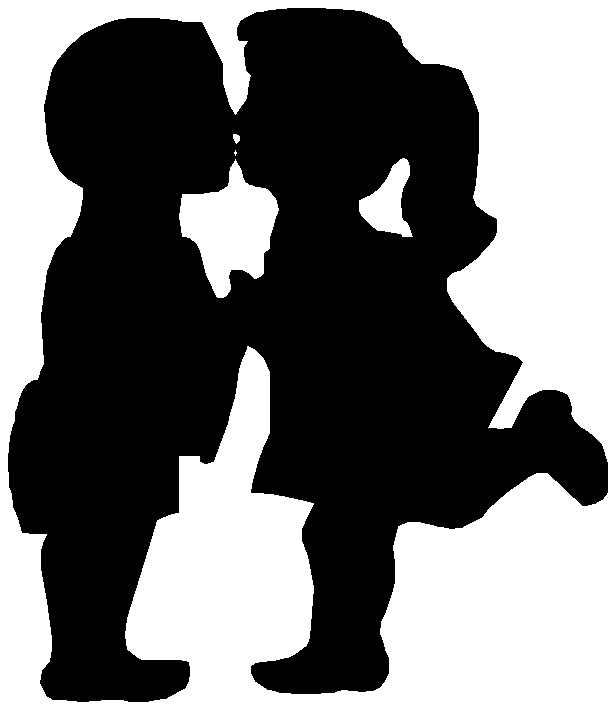 |
�O���S���k���A�X�� |
| �@i�[�����}���`�J |
|
| �@�@�@�@ |
 |
�O���S���͓샊�A�X���i���`���j�Ɩk���A�X���ɕ�����Ă���B
�샊�A�X���̗����암�́A���A�X���C�݂̐Â��ȓ���]�Ɩ��̕ω��ɕx�C�݂ŁA
�k���A�X�������k���́A�k��R�n���f�R�ƂȂ��Ă������ɑ����m�ɗ������ލ��s�ȊC��
2005.9.7�`9�̂R���ԂŁA�k���A�X���ɏ���茧�̎O���C�݂�K�ꂽ�B
�k���A�X���͊�茧�{�Â���X���v���܂ł́A��71�����P����
�����͖��l�w�ƂȂ��Ă���B
�C�݂������𑖂�A�܂��g���l�������ɑ����̂�
�ԑ�����̂��炵���i�F�������Ƃ͂�����B
���Ɋό��K�C�h�ɏ���Ă���S������̊C�݂̌i�F�́A�Ɍ����Ă���B
�����Ă̊ό��X�|�b�g�́A���p�����܂߂���ʂ̕ւ������̂ŁA���O�̒������K�{�B
�ӊO�������̂́A�V�R����͏��{�̓�����I�ȗ��قP�������ŁA
����ȊO�ɖk���A�X�����ɂ͂Ȃ��A�Ƃ������Ƃł������B
�K�ꂽ�ŏ��̓��́A�җ�ȑ䕗�P�S�������k�ɏP��������ŁA
�ꎞ�͂ǂ��Ȃ邩�Ɖ��l���o������Ƃ��S�z���肵�Ă������ł��������B
| �O���C�݂Ƃ́F�����ېV�ʼn��B���T�����ɕ������ꂽ�Ƃ��A�����i�X�`���k���j�E�����i��茧�̑啔���ƏH�c�̈ꕔ�j�E���O�i���암�`�{��j�̎O�����̂��ĎO���ƌĂсA���ˎs�L�肩��{�錧���������܂ł̊C�݂��O���C�݂Ƃ����B |
|
|
| �k���A�X���w |
| �{�� |
��̓n |
���a�� |
�c�V |
�ۑ� |
���{ |
���z |
�c�씨 |
���� |
����C�� |
�x�� |
��c�ʐ� |
������c |
�����F�� |
�v�� |
| ��y���l |
. |
. |
�O���� |
. |
. |
. |
�k�R�� |
. |
. |
. |
���ڂ���E���x�R�N���_ |
. |
�瑐�X |
|
|
|
|
2005.9.7���k�V�����͂��3���œ����w���V�F56�ɏo�����A10�F22�ɐ������B
�ݗ������D�i�ʐ^���j���o�AJR�R�c��4�ԃz�[������10�F48���������A�X���ŏo�����A12�F48�{�Éw�����B
�{�Éw�z�[���i�ʐ^�E�j�ɂ͊m���ɎO���S���i�k���A�X���j�̈ē�������A���̑����ݏo�����B
�@�@�@�@ |
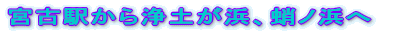 |
 |
�{�B�œ��[�Ɉʒu����s�s�{�Â̒n���R��
�{�Éw���琼�֓k��5���̂Ƃ���ɂ������R�����_���́A�h�{�Áh�̒n���̗R����`����ÎЂŁA
1011�N�i���O�W�j���R�����_�Ђ��K�����A���g�̖�̖���_�̂�����Ē��߁A
���V�c����h�s�h�Ɠ����Ăі��̂Q�����������̂��A�R���Ƃ����B
���R�����{�͋`�o��]���Q�q���h���������Ƃł��m���Ă���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |
|
|
���̂���͒��Nj��̑䕗�P�S�������{�S���𑛂����Ă������ŁA
���̓��͓��k�n���ɍŐڋ߂������ŋ{�Â͉J�A���̓V��s�ǂŁA��͈�ʈÉ_���Y���Ă����B
���悢��{�Éw����k����3.5�����ɂ�����y���l�֏o���B
JR�{�Éw�i�ʐ^���j���o�Đ��ʂ��^�����ȑ�ʂ���k��100���قǕ����A
����s�̌����_�i�ʐ^�E�j���E�܂��ă��C���X�g���[�g�̏��X�X�𓌂ɐi�ށB
���X�X�ł͑剹�ʂłȂɂ��̗̉w�Ȃ𗬂��Ă���̂ŁA���ƂĂ����C�����������邪
�悭����Ǝ��ԑт����邩������Ȃ����w�ǐl�ʂ�͂Ȃ��B
�@�@�@�@ |
|
|
���C���X�g���[�g���700���������V�쒬�������i�ʐ^���j�̂�������_�ƂȂ�A
��y���l�ւ͒��i���������������S�T�����i�ʐ^���j�ƂȂ�B
�������̉E��ɂ��{�Îs�������A�בR�Ƃ��ė��B
�@�@�@�@�@ |
|
|
�����150���قǕ����P�O�U�����Ƃ̒����H�ƂȂ�A�E����̉����q���ڋ��a���̗���������B
�q���ڋ��a���͗��̌Ǔ��ł����Q��ŋꂵ�ނ��̒n�����~�����߁A�O�����݂̊C�l�����͂���
�{�Â��琷���܂ł̉��H�i���P�O�U�����j�̊J��ȂǁA���U�Ŗ�400�����̓��H�Ɍg������̐l
�@�@�@�@�A |
|
|
�i�ނƉE��ɂ͍�����S�����h�g�畻�������A
�J���Ă���傩���O�֏o��ƕɐ�͌����{�Í`���J�ɉ���B
�Ȃ��h�g��͖����Q�X�N�ȗ��ĎO�P��������Ôg��Ō��݂��ꂽ���́B
�@�@�@ |
|
|
���̐�������M���̒����H�i�ʐ^���j�ŁA�S�T�����͍��܂��������������⓹��o��B
��y���l�ւ͒��i���A���ɕ������Ƃ���ł͉E�̓���i�ށB
�@�@�@�@ |
|
|
���܉J�A���������Ȃ�A���ɂ��炵���i�F�ł��Ȃ��A�����Ђ�����O�ɐi�ނ����B
���ݒn�o�X����߂���ƁA�O���Ɂu�E�o��u���A���i��y���l�v��ʕW���i�ʐ^���j����A
���̐�̋{�Îs���s�ꂩ��E�܂��āA�`�����傢�Ɣq�����������D�͑����Ōi�F�͓܂�B
���̓��ɖ߂�A���ɗX�ǁA�E�ɃT�C�������Ȃ����Ս`�ʂ���i�ށB
�@�@�@ |
|
|
�Ⓚ�H����߂��A�E��̐F�ʊ��o�̂��錚�����`������O��i�݁A��y���l�̈ē�������E�܂���B
���X�����č��E�����`���������B�ꂷ��B
�@�@�@�@ |
|
|
�₪�����͂Q�ɕ�������i�ʐ^�E�j�̂ŁA����̓���i�ށB
��y���l���W�i�ʐ^�E���j�����Ȃ���A�l�֍s���Ƃ����̂ɗΑ����R����o��Ƃ����A���̈�a���B
�₪�ē��̒���炵���Ƃ���Ɂu���i�@��y���l�v�ē���������A�i�ނ���꒓�ԏ��ɏo��B
�@�@�@�@ |
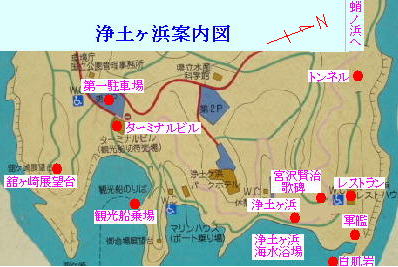 |
|
|
��꒓�ԏ�L��̉E���ɂ���A�u�����̓��v���W�i�ʐ^�E�j�ɏ]���K�i��o���Ɛ��ʂ�
�u���F�ڃ���W�]��95���v�u�E�F���_��W�]��410���v���W�i�ʐ^�E���j�������Ă���B
���܂��Đi���i�ʐ^�����j�A���ʂ������ȍL����������B
���_��W�]��ւ��s�������r���ׂ��������ŋ����ɉ�A�ؚ��Ȏ��̑̂ł͂ƂĂ������Ȃ��ƒ��߁B
�@�@�@
|
|
|
�L��ɂ͑S���l�e�̂Ȃ��n��V�����W�]�����|�c���Ɨ����Ă���B
���������Ύs�X�n�𗣂�Ă���S���l�Ԃɉ���Ă��Ȃ��A�������䕗�ł���B
���킲��W�]��ɓo��A�ō��̌i���ƂȂ�͂��̍��E���C�Ɠ��Ɣ������}���ŎB��܂������B
���X�ɑ�꒓�ԏ�ɖ߂�B
��͂�l�e���F���̊ό��n�͈ٗl�ł��邪�A�߂������ƂɎ��̃X�P�W���[���͕ύX�s�B
�@�@�@�@ |
|
|
���ԏ���悭����ƁA���̂ق��ɐ���Ԃ����蓯��������ޓI�ɉ��ƂȂ����S����B
���ԏ���ɂ���A�^�[�~�i���r���։��鎩���̔��@�e�̊K�i���~����
�r����y���l���W�Ɛ��ʂɂ��i�Ǝv�������j�C�̐F�B
�@�@�@�@ |
|
|
�~�肫����V�����i�ʐ^���j�����荶�܂��Đi�ނƁA
�ˑR�u�{�[�v�Ƃ����D�J�ƂƂ����V���D���˒�̊O�֏o�čs���Ƃ���B
����ȋ����̒�����J�Ȃ��ƂƁA�D��������Ɛl�e�����炿��ŁA�������łƐS�ŋF��B
��ɐi��2�ɕ�����铹�́A������g���l�������B
�@�@�@�@ |
|
|
�g���l�����߂���ƁA�l�璹����H�߂��B
���̕ӂ����y���l�i���̕l�j�Ƃ̂��Ƃł��邪�A�e���r�Ō���i�F�Ƃ͉����Ⴄ�悤�ȁB
����ɗV����������Ă܂��g���l�������B
�@�@�@�@ |
|
|
�C�͓���������������Ɍ������V����������ɐi�ށB
�@�@�@ |
|
|
�O�����J���Ċ�O�������l���Ƒ召�̘A�Ȃ������┧���W�J����B
���������^�����̏�y���l�ŁA�m���Ɏʐ^�Ȃǂł݂��悤�Ȍi�ςł���B
����ɂ��Ă��A�����̂��ƍ��ɂ̊C�ł���A���������͂������肩�Ǝv���B
��y���l�̒n���R���F��R�O�O�N�O���̒n������������Z�E�싾�a�����u��y��������v��
�̂������Ƃ���A���Â���ꂽ�Ɠ`�����Ă���B�l�ӂ���y�A�O�C��n���Ɍ����ĂĂ���B
�l�̔����́A�Ήp�e�ʊ�Ƃ�����Ŋ₪�Q�ŐN�H���ꂻ�̂����炪�l�ɑł��オ��ꂽ���́B |
�����Q�x�ƖK��邱�Ƃ��Ȃ������m��Ȃ��A���̔����l�����\���ĕʂꂽ�̂ł������B
�Ȃ����̕l�ŋv���U��ɐ��l�̐l�Ԃ����ɉ���Ƃ��ł������Ƃ��A���L�Ƃ��Ă���B
�@�@�@ |
|
|
�����┧�̕t�������������Ƃ������i�ʐ^���j�̉���
�E���ɂ́A�P�X�U�O�N�T���Q�S���`���n�k�Ôg�L�O��������
�����ɂ́A���Ɣ����~�j�`���A�R�D����y���l���X�g�n�E�X���o�b�N�ɒu����Ă���B
�����Q�N�{�Øp�̋ߑ㏉�̗m���C��Ŏg��ꂽ�R�͂ŁA�������{�̉�V�A�������R�̍b�S�ł���B
| ��V�F�C�͖ؑ��A�S��72���A��11���A����12�\�A�P�W�T�T�N�v���V�������i�C��œy���ΎO����D�j |
| �b�S�F�C�͓S�D�A�S��65���A��10���A���͂W�\�A�P�W�U�S�N�t�����X�����A�@�֏e���� |
�@�@�@ |
|
|
���X�g�����O�̓��H�̓����̍����Ɂu�E�F���m�l�@0.4�����v���W�i�ʐ^���j������A
���̘e�Ɂu����킵�́@�C�̃r���[�h�@���z��́@����̂͂܂Ɂ@�~����Ђ���ʁv
�ƍ��܂ꂽ�{���̉̔�����������Ă���B
���X�g�����̉��O���̋@�Ńh�����N���w�����Ă���Ƃ��ˑR�җ�ȉJ�A���B
�����b�N�T�b�N����o���Ă������n�}�Ȃǂ����������т���ʂ�ŁA�����Ă��܂��C�����B
���m�l�֍s�����ߓ��W�ɏ]�����i���ƏƖ��̂��Ă��������g���l���ŁA�����͐��Z���œ]�|���ӁB
�@�@�@ |
|
|
�g���l�����o��������C�ݎ��R�����̕W���i�ʐ^�E�j�������Ă��āA���̃g���l�������̒��ԁH
���܂��Ċ�̊Ԃ̓���i�݁A�O�������˓��H�Ƃ��̉�����������������B
����ɐi�ނƑΊ݂ɊC�����ꂪ������̂ŁA�������ꂪ���m�l�i�ʐ^���j�̂͂��B�i�l�����Ȃ��̂ŕ����Ȃ��j
�J�ɔG�ꂽ�C�݉����̓�������ƁA���Β��ӂ̗��D�����茻�ɓ��ɂ͑召�̊���S���S���B
���낵���Ȃ�A������Ȃ�����ɂ͋삯���B
�@�@�@ |
|
|
���̏I�����i�ʐ^���j��n��A�g���l�������ƕ��}�ȍ��l������B
�������������m�l�ł��낤���A���̎����킴�킴�K�˂邱�Ƃ��Ȃ������悤�ȋC�������B
�@�@�@�@�@ |
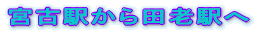 |
|
|
���m�l����ʘH�Ŗ߂�r���A�S�����R�A�V�̏����Ŗڂ̑O�Ń^�N�V�[����q���~�낵���ł͂Ȃ����B
�������̃^�N�V�[�ŎO���S���{�Éw�n��16�F12�ɃW���X�g�Z�[�t�B
������A�n���ł̓o�X���d�Ԃ��P���ԂɂP�{���x�����Ȃ��̂ŁA���Ԃ͂����Ŕ��������Ȃ��B
�O���S�����{�Éw�́AJR�{�Éw�ɗאڂ��Ă�����̕����O�ς͗��h�Ɍ����邭�炢�B
���̉w�ɂ̍����ɁA�O���S���̊J�ʋL�O������������Ă���B
���悢���O���S���k���A�X���ł̗����n�܂�B
��Ԃ����d���́A�ɕ��ʂ̓d�ԁB
�e���r�Ō��������~�d�Ԃ́A�n���̐l�������邩�m��Ȃ��Ƃ����B
�@�@�@ |
|
|
16�F30�J�̓c�V�w�i�{�Îs�j�ɓ����B
�z�[���͍���ɂ���A�K�i���~��ďo���ɏo��ƁA�h������O�����s�A�[�c�V�̌}���̎Ԃ��҂��Ă����B
�Ȃ��{�Éw����c�V�w�܂ł̏�i�`�ʂ��Ȃ��̂́A
�d�ԂŒn���̖���̉��l�Ɨ����ɂȂ��Ă��܂��A�b���e��ł���ǂ���łȂ������̂ň������炸�B
�@�@�@�@ |
|
|
���ꂽ��̗��X���W���ēx�c�V�w����o�����āA�������O�����܂ŁB
�w�O������177�����i�ʐ^���j��k���֍⓹��o��ƁA������c�V�w�̃z�[����������B
�˂������̒����H�ō��܂��č����S�T������i�݁A��500���s����
�u�O����A�^��C���v��ʕW���̐�́A�{�ÐM�p���ɂ̌����_���E�܂���B
�@�@�@ |
|
|
�����i�ނƐ��ʂɍ���10.65m,������2433�������{��̖h�g����������B
�o���Č���Ƃ܂��ɓV��̓h�C�c�Ȃǂ������s�s�̏���i�ʐ^���j���v�킹����̂�����B
�����Q�X�N�Ə��a�W�̎O����Ôg�A���a�R�T�N�̃`���n�k��Ôg�Ɠx�d�Ȃ�Ôg��Q�̑�Ƃ���
���݂��ꂽ�h�g��ŁA���̎O���C�݂ł����������Ă���B
�@�@�@ |
|
|
�J���Ă����Q�[�g������Đi�ނƓ��͒����H�ƂȂ�A���i����B
�ό��D�����ۏ�D����̔����Ă������Y�Z���^�[�O��ʂ�A�c�V���ɂ������O�{�ꋴ�ɏo��B
�c�V����T�P�}�X���B�͐��i�ʐ^�E�j�Ƃ��ė��p����Ă���B
�@�@�@ |
|
|
����n����L���i�ʐ^���j������A�����ɂ͂��������݂Ȃƌ����A
�E�ɂ͓c�V�z�R�R��c�V��������B�͐�Ƃ��Đ��������A�{�B��̍����㐔�ƂȂ������Ƃ��L�O����
���̃��j�������g����������Ă���B
�@�@�@ |
 |
���ʚ��̊ݕǂ́A�c�V�Ə�y���l�Ԃ��ό��D�������ŁA���܂��������������D���Ă���B
�@�@�@�@ |
|
|
���̂Ƃ���ɖ߂荡�x�͒����H���E�܂����꒼���̓���i�݁A�E�ɓ�����c�V�`������B
�@�@�@ |
|
|
���̓˂���������h�g���ŁA�J���Ă��������O�֏o��B
�h�g��̓V��ɓo�蒭�߂�ƁA�E�ɍ������꒼���̓��A�������c�V�`��������B
�@�@�@ |
|
|
�h�g��̊O�֏o�ĉE�܂��A�u�����C�ݍ��������O���v�Ŕ̗����⓹�Ȃ�ɓo���čs���B
���炭����ƉE�����W�]��֒ʂ���ׂ���������A�W�]�䂩��͍������t���̎O������������B
�@�@�@ |
|
|
����ɓo�葱���Ă�ƁA�E���ɂ�����̓W�]��ɒʂ����O���V�����i�ʐ^���j�����邪�A
�䕗�ɂ����̂������ɖ��|��Ă����肵�Ă��Ă��邽�߁A�������\���グ���B
���̐�������h�ɎO���t�̒��ԏ�����ቺ�̎O���C�݂ɓW�J�����O�����́A�ƂĂ������I�Ȕ������B
�O����:
|
����50���̒j��A�T��̏���A�⑾�ۂ̌`���������ۊ�̂R���̂��ĎO����Ƃ����B
�j��ɂ���C�H������蔲����ƍK�^���K���Ƃ������A�C�������ǂ�����Ă�����H |
|
�Ƃ���ŁA�����̍����h�ɎO���t�ɂ͑S���l�e���Ȃ������H���h�������Љ�ی������݂�
�O�����s�A�c�V�͖~���߂���Ƌq�����O���Ə��Ȃ��Ȃ�Ƃ������A�ǂ�����̎Z�����Ă���̂��S�z�B
�@�@�@�@�@�@�@ |
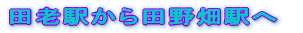 |
|
|
�k�R��f�R�ό��̂��߁A�c�V�w��9�F34�œc�씨�w�֏o���B
�d���͋{�Éw�ŏ�����^���Ɠ������́B
�@�@�@ |
|
|
�k���A�X���́A�����g���l�����i���������w�̌J��Ԃ����T�^�I�ȃp�^�[���B
�S���i�ʐ^���j�́A�Q���������B
���������̋�Ԃ��C�݂��痣�ꂽ�����������𑖂邽�߂��A
�₽��Ƀg���l����,����������g���l��������������Ɗ��҂𗠐�i�F�ƂȂ�B
���Ȃ݂�1,000�����g���l���̐��͍ł�����6,532���̃g���l�����͂��߂ƂX����������
�{�Á`�v���Ԃ�50���ȏオ�g���l���Ƃ����Ă���B
�@�@�@ |
|
|
9�F58�c�씨�w�i�c�씨���j�ɓ����B
���l�̉��D���o��Ƒ傫���w��������A���̒��̃R�[�i�[�ɐؕ�����ꂪ����B
�����̘e���{���̔����D�D�̈�߂�����������A
���̗����Ɂu�J���p�l�����E�c�씨�v�w���͋{���̋�͓S���̎�l���̗F�l�J���p�l�����̂悤��
�ア���̂������������̂ɗ����������E�C����l�ނ������瑽���y�o����悤�ɂƊ����
�{�����a�S���N���L�O���ĕ���9�N�ɖ��������A�ƗR�������܂�Ă���B
�@�@�@ |
|
|
�w�O��10�F05�̃}�C�N���捇�o�X�ŁA4�l�̏�q�ƂƂ��ɖk�R��֏o���B
�����Ɍ�����w�O�����˓��H��ʂ��ĉw���k�֖�10�����A�o�X�Ŗ�20���A
�u�����C�ݍ��������@�k�R�蒓�ԏ��v�Ŕ��̘e��ʂ�A���������y�Y���̑O��ʂ����W�]��������B
�@�@�@ |
|
|
���ɐi�ނƉE���Ɂu�k�R�艀�n�ē��}�v�Ɓu�������Ɩ�z��(�`���j�v�Ŕ�����ŗ��B
�̔������A�C�k���ɗ���������҂��A���������邽�ߒf�R�̖������Ŗ�ׂ������Ƃ�
1�l�̎�҂̖���i��z���j�������z���ď����ɓ˂��h����A���ꂪ��|�ƂȂ茻�����Ă���Ƃ����`���B
�Ŕ̐�͏�������ƂȂ������W�]���i�ʐ^���j�ƂȂ�B
�E����k�R��̒f�R�����̍r�X�����p�������Ă���B
�@�@�@�@ |
|
|
������Ɩ߂��E���̘e���i�ʐ^���j����A�K�i�����������đ��W�]��������B
���W�ł́A���W�]��܂ł�0.2�����A363�i�A�C�݂܂ł�0.4�����A718�i�Ƃ���
�r���A�E���֍~���K�i������A�u�k�l��3.5�����v���W�i�ʐ^�E�j�������Ă��邪�A�����͒��i����B
�@�@�@�@ |
|
|
�₪�đO�����J���āA���̕����W�]����������B
�������猩���k�R��̒f�R�́A���W�]��������̌��������悭�킩�邪�A
�����̂��Ƃł������Ɉ�w����������̂ł͂Ȃ����Ǝv���B
| �k�R��f�R |
�����C�ݐ���̌i���n�ŁA����200���̒f�R��ǂ������肽���A�W�����ɓn�葱���B
�U���ɂ͖{�B�C�݂ł�3���������炩�Ȃ��Ƃ����V���o�i�V���N�i�Q���ʂ��Y����B
�C�ォ��́A���z�`����k�R�菄��ό��D���o�Ă���B |
|
11���߂��Ɋό����I���A��̃o�X���Ԃ�����ƁA�Ȃ�Ǝ�����13�F23�B
�����Ŏ��Ԃ��Ԃ��悤�ȂƂ���͌������炸�A
����o�X�ňꏏ��������������̈�l���̒j�Ɗ��芨�Ń^�N�V�[���ĂԂ��Ƃō��ӂ��A�v3600�~�B
�n���ł́A�����̂��ƂȂ���{���Ɍ�ʋ@�ւ̏��p�����������A����������������Ȃ��ƒ��߂�B
�@�@�@�@�@�@
|
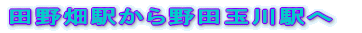 |
|
|
�c�씨�w���w���i�ʐ^���j�����߂Č���ƁA�m�Ɂu���̂͂��v�̏�Ɂu�J���p�l�����v�̕���������B
12:45���̂Q�q�Ґ��d�Ԃ������������A������܂������^���d���B
������ƃr�b�N�������̂́A�ԓ��̔��̐l�i�ʐ^���j���i������t��葵���ď�荞���ƁB
�S�z�����Ƃ���A�ԓ��̏�q�͋ɏ��Ȃ��m���������Ȃ������悤�ł���B
��荞��ł���ȏ�ɋ������̂́A�v�������Ȃ����l�^�]�����j�b�R���Ί�Ō}���Ă��ꂽ���ƁB
�����}���J�[�łȂ������E�[�}���J�[�ŁA�ޏ������邾���Ŏԓ��͋}�ɖ��邭�Ȃ����悤�ȋC�������B
��͂�^�]��͏����Ɍ���!?
�@�@�@ |
|
|
���̋�Ԃ͊C�݂ɋ߂��Ƃ��������A�C�̌i�F��x�X���邱�Ƃ��ł���B
�@�@�@�@ |
|
|
13�F13��c�ʐ�w�i��c���j�ɓ����B��q�͂Ȃ��A�~�q�͎��P�l�B
�d���̑O�ŃJ�������\���Ă�����A���l�^�]��͎��Ƃ̕ʂ��ɂ��ނ悤�ɒ��X�o�������A
�悤�₭�������Ɠ����Ĕޏ��̓K���X�z���Ɏ��Ɍy����߂����Ă����̂ł������B
�i���X�A�P�ɃJ�����T�[�r�X�̂��ߔ��Ԃ�x�炵���H�����I�ɔ��f�����ꂪ�ł������I�ȍl�������m��Ȃ��ł��ˁB�j
���l�̉��D���o�āA�������w�ҍ������B��B
�@�@�@�@ |
|
|
�w�O�͑S�����G���L���ŁA�l�̋C�z���Ȃ�������45�����������Z������邾���B
���s���~����K�˂邽�߁A�w�Ɍf���Ă������ό��ē��}�]�������������ɓ��B�ł��Ȃ������B
�ȉ��͎��͂ōĒ��킵���L�^�B�i�ʐ^�͈ꕔ�X���ɎB�e�������́j
�w�O�̍���̓�������A�r������U�^�[���Ő܂�Ԃ����k���A�X���̃K�[�h������Đi�ށB
��������̂ŁA�U��Ԃ�Ɩk���A�X���̂���܂ł̐F�ʂƈقȂ��d�����ʂ�߂��čs���B
���ʂȓd�Ԃ������̂��낤���B
�@�@�@�@ |
|
|
���Ȃ�ɉE�։E�ւƍ⓹�������ƁA�S���l�e�̂Ȃ��ʐ싙�`�̑O�ɗ���B
���s���~�Ղ֍s���ɂ͂������炪��J����Ƃ���ŁA�ē����Ȃ��q�˂�ׂ��l�����Ȃ��B
�����͋��`�̑O���E��̏������u�ɓo��⓹�����s���~�Ղւ̓����ŁA
�o���čs���Ɠr���Ɂu�@�ʕ����v���D������B
�@�@�@�@ |
|
|
����ɂ�����Ɠo��ƁA�E��������ȍL�������肱�������s���~�Ղ�
�������s���~�̕W���A����ɍ���O�ɂ͌Â��������s���~�ՐΔ��������Ă���B
���s�����̒n�̋ʐ�C�݂̔������i�F�ɖ������āA�������������Ƃ���ŁA
�ȑO�͂����ƍL���������u�ł��������A�n�Ղ��������ď������Ȃ��Ă��܂����Ƃ����B
�@�@�@�@ |
 |
���s��������ꂽ�Ƃ����ʐ�C���߂�ƁA���͋ʐ싙�`�����ɂ̊C�ɉf���Ă���B
�@�@�@�@ |
|
|
�⓹�ɖ߂�E�����ʐ�_���̑O��ʂ�A�k���A�X���̉�����������S�T�����ɏo�āA���܂���i�ށB
�@�@�@�@ |
|
|
�S�T�����͂�邢�o���ƂȂ蒸��߂��ŁA�ቺ����C������˂��o�Ă����G�X�q����������B
�G�X�q��͋ʐ�C�ݑ�\����i���n�ł��邪�A�C�݂ɓ����Ȃ��̂Œf�R���炵�����邱�Ƃ��ł��Ȃ��B
����ɏ����i�ނƁA�E����T�P�̎q���̃C���[�W�L�����N�^�[�̂�������}���Ă����B
�h�����鍑���h�ɂ��ڂ����́A��������E��̍��o���Ă����B
�@�@�@�@ |
|
|
�S�T�����͍��x�͏��X�ɉ����ƂȂ�A��������Ƃ���ɂ�����Ɛ�ɂ��������Ƒ勴��n��B
����ɂ������Ƌ��`�A�E��ɂ����Ɛ�Ɩk���A�X���̉���305���̓S����������B
���Ɛ�́A���n�͐�̌k���ނ�̐�Ƃ��đS���I�ɗL���ŁA
�܂��T�P�E�}�X�Ӊ��ꂪ����P�͐�Ӊ��\�͓͂��{��B
�@�@�@�@�@ |
|
|
����n��E�܂��Đ�̏㗬�i�ށB
�ɋ߂��Ō����S���̋��r�͂ƂĂ������Ă����܂����A�卪���̔�ł͂Ȃ������B
�܂��C��w�ɂ��Č���k���A�X�S���́A�悭�ό��p���t���b�g�Ō���p�ŁA�������������̏ꏊ�̂悤�B
�@�@�@�@ |
|
|
������E�܂���100���قǂ̂Ƃ���ɁA�������������Ƌ��i�ʐ^�E�j���������Ă���B
���̒�����������J�����̎ʐ^���B�낤�Ƃ���ƁA����萠�̃T�P�̑��̏�Ɉړ����Ă��܂���B
������A����ό����ꂵ�Ă���ȁH
���̐�̏㗬���ɁA�T�P�̂Ӊ��p�Ǝv���鋐��Ȏ{�݂�������B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |
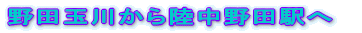 |
|
|
�����͂X���X�������Ď��̒a�����B
��͂���ȏ�̐����Ȃ����炢�ɐ���オ��A�������������j�����Ă���Ă���悤�ŁE�E�E�B
��c�ʐ�w�����̕W���������Ă��������S�T�������A�k������������c�w�܂ŕ����B
�Α����S���l�e���Ȃ��A���܂ɎԂ��ʂ铹�H�́A�����̂ɍō��̏����B
��䂩��341�����̕W�����݂Ȃ���A���K�ɕ�������B
���̂Ƃ��A�ˑR���̘e�ɏ�p�Ԃ��ߊ��u�悩������ǂ�������čs���܂��v�Ɛ��������钆�N�̒j�B
�����̃V�[�g�J�o�[������Ă��܂��قǂ݂��ڂ炵�����p�̎��ɁA�킴�킴���������Ă��ꂽ�l�B
�X�����������Ă��邱�Ƃ���������D�ӂ�L����f�肵�����A���������e�͏��߂Ă̌o���B
����͒a�����̃v���[���g�H
�ʐ^�E�͂��̂Ƃ��̏ꏊ�ŁA�L�O�Ƃ��đ�ɂ������B
����ɂ��Ă����Ƃ����Ƃ���́A���l�����łȂ��A���N�̔��j�q�����������Ƃ��Â��v���̂ł����B
�@�@�@ |
|
|
�S�T�������C�݉����ƂȂ�A�����O�����O�蔼����������肱���������v���͂��̌����ɂ���B
�ēc��͌��t�߂ɂ́A�l�H�̊C�������i�ʐ^�E�j������B
�@�@�@ |
|
|
��c�ʐ�w����R�����قǗ���ƁA�S�T�����̉E�����ȒÊC�_���̎�F�̒�����������B
�����̍��ɂ́A�u�����C�ݍ��������\�{���Y�v��������A����ꂳ��Ă��Ȃ����ڂ��ڂ��̋����ɂ�
�u�݂��̂��̂Ƃӂ̐��������ӂɂ͌N���˂����Ă݂ӂɉ�˂�v���r�ݐl�m�炸�̋��������B
�@�@�@ |
|
|
�u��c���x�R�̓��N�_�v���݂邽�߂ɂS�T�����𗣂��_�Ђ̉E���̍⓹��i�ނƁA
�O���͌Â�����̖��ɓo�ꂷ��G�̂悤���\�{���Y�̔������C���ƂȂ�B
�����i�ނƉE���Ɂu�\�{���Y�v�W���Ɓu�\�{���Y�C�l�̐X�ē��}�v��������A��������X�֓���B
�@�@�@ |
|
|
�C�݉������X�͂悭��������Ă���e���̏�ŁA
�N�����Ȃ��̒����v����[�ċz�����ăt�B�b�g���`�b�g�i���Ă��炭�����B
�₪�ăg���\�[���̖`���̂悤���X�̒��̏����������Ă���A
�����̑O�ɂ͉��̂��r������A������G�ɂȂ镗�i�B
�@�@�@ |
|
|
�r���E���I�铹�i�ʐ^���j��i�݁A�C�݂ɒʂ����������̒����H�ɏo�āA���܂���B
�����̃O�����h�����ɐi�ނƊp�̂Ƃ���ɐ����ƂƂ��Ɂu��c���x�R�̓��N�_�v�Δ�������B
�����̂����c�ɂ͑����̉���������A
��c�Ő������ꂽ���̓x�R�i���j�̔w�ɏ悹�āA�����k��R���≜�H�R�����z���ē����ɉ^��Ă����B
�������牖�s�������o������Ƃ�������x�R�̓��Ƃ������A���̒n�_��X�I�ɋN�_�Ƃ��Ă���B
�@�@�@�@ |
|
|
���̂܂����i�i�ʐ^���j���A�h�g��ƂȂ��Ă����S�T�����̖����ʂ蓹�Ȃ�ɉE�܂���������H�ɂȂ�B
����ɉE�܂��Đi�ނ��S�T�����Ƃ̒����H�i�ʐ^�E�j�ɂȂ�A���܂��Ėk���ɐi�ށB
�@�@�@�@ |
|
|
���̉E���ɂ̓R���N���[�g��������Ȑ���������A���Α��̕���������������ׁX�Ɨ���Ă���B
�Ôg��ŁA���̂悤�ȏ���ɂ�����Ȑ����ݒu���Ă��āA���H���ђʂ��鏬��ɂ͑S�Ă���B
�O���ł͓x�d�Ȃ�Ôg��Ƃ��āA�R���N���[�g�̖h�g�����邾���łȂ��A
���R�̒n�`�𗘗p�����R��A���H�A���H�Ȃǂ̍������h�g��Ƃ��Ċ��p���Ă��鏊�������Ɍ�����B
�₪����c������̕W����������ƁA�}�ɏZ������Ȃ�B
�@�@�@ |
|
|
����ƉE���������c�w����������Ă������̉w�̂��̂ЂƂ��͖ڗ�����������B
��c���x�R�̑��̑O��ʂ�Ƃ����������v���s�̋��E�W���ŁA���̉w�͋��E�Ɍ��݂���Ă���B
�@�@�@ |
|
|
���݂���Ă���������c�w�i�ʐ^�E�j�ŁA�v���w�܂ł̐ؕ����w�����z�[���֏o�����A
�Ȃ�ƒn���̐l�������������[�̓�������D��ʂ�Ȃ��ŁA���ڃz�[���֏o�Ă���ł͂Ȃ����I
�m���ɖ��l�w����̖̂k���A�X���ł���A���ɉ��D���o�Ȃ��Ă��悢�킯�ŁA�[���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |
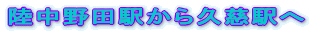 |
|
|
������c�w��10�F25���d�Ԃ�҂��Ă���ƁA�܂��������^���̓d���B
�����悤�ɂ��Ɉ͂܂ꂽ���H�𑖂�B
�@�@�@�@ |
|
|
�Q����v���w��10�F43�ɓ����B
�z�[���ɂ͕��̔z���ōw�������Ƃ����A��������Ԃ̂悤�ȓd������Ԃ��Ă������A
����ȓd�Ԃɂ�����Ă݂��������B
�K�i�̏�����ɁA�u�s�v�c�̍��̖k�A���X�v�̑傫�ȊŔ́A����������U���B
�@�@�@ |
|
|
�w�����o��ƁA
�n���o�g�����c�όu�̉̔��i�ʐ^���j�Ɓu�O���S���k�A���X�������Ɏn�܂��v�L�O���B
�k�A���X���̊J�ʋL�O��́A���낢��ȉw�Ɍ�������Ă��ĊJ�ʂ��ƂĂ����ł��邱�Ƃ��`���Ă���B
�@�@�@ |
|
|
�w�̐��ʂ̌����ł́A���肩�犽�}�����̐^���Œ��B
�i�q���ː��v���w�̔��ˉw�s�d�Ԗ{���͈���킸���X�{�����ŁA12�F54�̈ȍ~��14�F45�A16�F51�ƂȂ�B
���������Ȃ�ł�12�F45�̓d�Ԃɏ�邱�ƂɌ��߁A���̊Ԃ̖�Q���ԂŎs���ό����邱�Ƃɂ����B
��鍑���h�ɂ��ڂ����Œm�荇�����v���o�g�����l���q�吶�i�S�R�}����ŏЉ�j����A
�s���͓��ʊό�����悤�ȂƂ���͂Ȃ����A�u�瑐�v�Ƃ������[�������̃��[�����͂��������������A
�Ƃ����ɔ������肵�Ă����̂ő������̓X�ցB
�O���S���{�Éw�O�̐^�������P�Q�S����������ƁA�E���ɂ�����ƋC�ɂȂ����������B
�@�@�@�@�@ |
|
|
�˂�������Ƃ݂��̂���s�̂Ƃ�����Q�W�P�����Ǝ߂ɍ����i�ʐ^�E�j���A�E�܂��Đ��i�ށB
��s����6,�V���ڂ̉E���ɁA�Ԍ��̋����u�瑐�v�̒g���B
���ɓ���Ɖ��s��������A�܂�11���߂�������Ȃ̂ɂ��������ȏ�̐Ȃ����܂��Ă���B
�Ȃɂ���葢�胉�[�����Ŕ���ꂽ��X��߂邢���B
�ݖ����[�����𒍕�������A�m���ɐ̕��̓��k�̃��[�����̖��B�R�N������܂��B
�܂��܂����Ԃ�����̂ŁA�s�������邱�Ƃɂ��āA������281����������ɐ��i�ށB
�@�@�@�@ |
|
|
����s�̂��鎟�̌����_���E�܂��ċv����ɂ��������̋���n��B
���̏ォ�獶���ɂ��v�����̗���A�E������ɂ͉���������Ȍ����B
�@�@�@�@�@ |
|
|
����n��ŏ��̌����_�̌�ʕW���̉E���Ɂu�������҂��v�Ə�����Ă�����̊G�A���ꉽ�̈Ӗ��H
�M�����E�܂��Đi�ނƉE���ɐ�قNj��̏ォ�猩������Ȍ���������A�s���̈���ł������B
����ɂ��Ă��A�s�̋K�͂ɂ͊W���Ȃ���������Ȃ����Ȃ�Ƒ傫�����Ƃ��B
�@�@�@�@ |
|
|
���̐�͔��ː����ׂ������ŁA���̏ォ�牺������Ɖ��Ƃ����P���A������Ɛ�ɂ͕��ʃN���X�̓��B
1���Ԃ�1�{���ʂ�Ȃ��d�Ԃ̂��߂ɂ��̑傰���ȗ����͖{���ɕK�v�������̂��ƁA�������^��Ɏv���B
�������ł������ߕ��s�҂͂킴�킴�K�i�̏�艺�����������B
�����Ȃǂ��Ȃ����߁A�������������Ƒ҂��Ă��邾���̑�s��̊J�����̓��ŁA
���ɂ͎��S���̂Ȃǂ����������ʎ��ԂƔ�r����ƁA���������Ȃ��B
�@�@�@�@ |
|
|
����������čŏ��̐M�����E�܂��A�v����̂���ǂ����勴��n��ŏ��̌����_�ɏo��B
�����ō����ɂ́A����܂��f���炵���|�p�I�Ȍ������B
�A�[�o���z�[���Ƃ����v���s������ق��Ƃ����B
�@�@�@�@ |
|
|
�M������E�܂��ċv���w�̗����������ƁA�������s�����̌����i�ʐ^���j�B
������܂�Ƃ������}�Ȃ��̎p�����āA���̂��ق��Ƃ����C�����ɂȂ����B
���̐�������_�i�i�ʐ^�E�j���w���ɏo�āA�n���������B
�@�@�@�@ |
 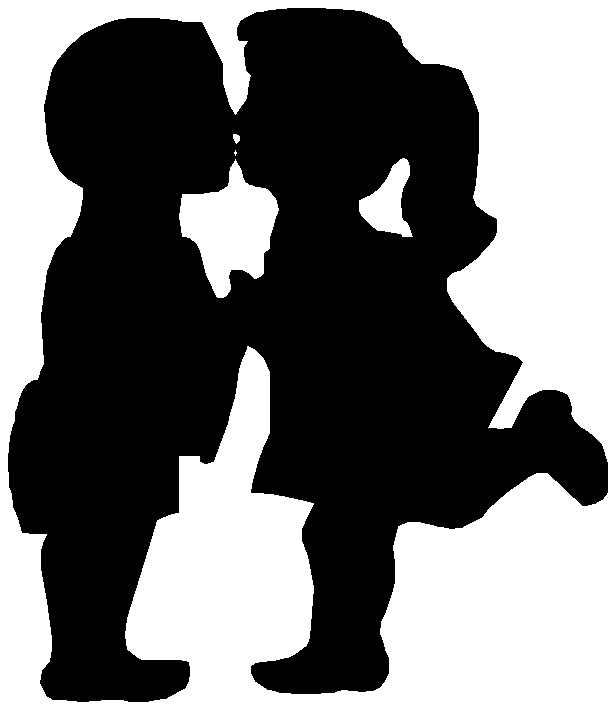 |
�n��������蔲����Ɖw�O�ɏo��B
�i�q�v���w�͎O���S���v���w�ɗאڂ��Ă��āA�O���S�����傫�ȉw�ɁB
����Ŗk���A�X���̗��͏I���ƂȂ邪�A�v���s���U��Ŏs�������s�̍�����Ԃ��킩�炸��
�����\�ʓI�Ȍ����ŁA�낢��ᔻ�߂������Ƃ��q�ׂĂ��܂������Ƃ�
������ƌ��߂����C�����ɂȂ��Ă���B
���O�҂̑f���Ȋ��z���q�ׂ����Ă�������������ƂŁA����������������Ǝv���B
�P�Q�F54�v���w���A14�F44���ˉw���B16�F04���˔����k�V�����͂�ĂQ�Q���œ����ցB
�@�@�@�@�@
|
|
| ������ |
�n���̐l�������k�A���X�����ƂĂ���ɂ��A�����ĉ����̊ό��ɗ͂����Ă��邱�Ƃ��悭�������B
���ł���c���͓��Ɋό��o�q�ɔM�S�ŁA��������@�Ŋό��X�|�b�g���Љ�Ă���B
�����c�O�Ȃ̂́A�]��ɂ��n�悪�L���ĕ����l�ɂ͎��肫��Ȃ��Ƃ������Ƃł���B
�����������ŁA�n�����m�o�n��c���x�R�̓��̃z�[���y�[�W�́u�n���w�̂����߁v�ŁA
��c���̂�����u����J�[�h�v�Ƃ������j�[�N�ȕ��@�ŋ��X�܂ŏЉ�Ă���B
���̃J�[�h���݂�Ζ�c���̑S�Ă�m�����悤�ȋC���ɂȂ��̂ŁA�����N�ŏЉ�����B |
�@�m�o�n��c���x�R�̓��z�[���y�[�W
�N���b�N���ĉ�������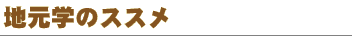 |
| �@�@�@�@�@ |
 |
| �@�@�@�@ |
| �@�@�@�@�@�@ |
| �@�@�@�@�@�@ |