| |
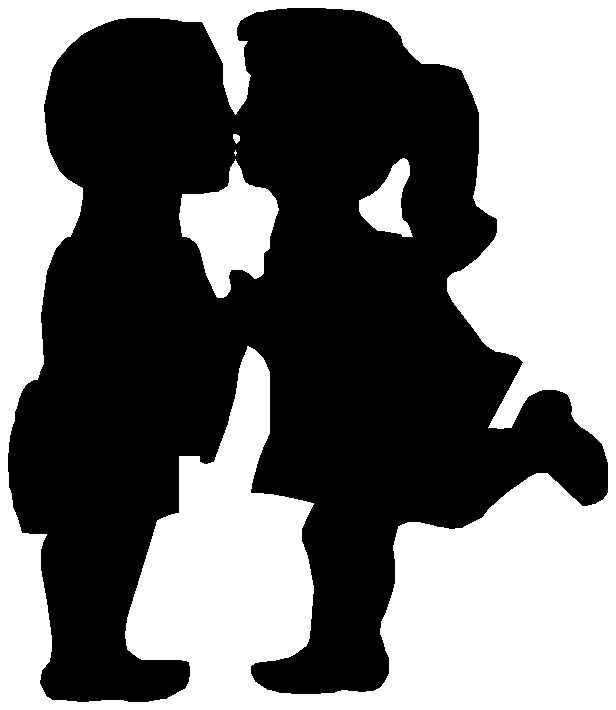 |
雨の室生寺 |
| iー愛ロマンチカ |
|
| |
 |
2004.8.23の小雨の日,奈良県宇陀郡室生村の
室生寺を訪ねた。
室生寺は昔から女性に門戸を開放し
女人高野と呼ばれている有名な寺院である。
小雨にしっとりと濡れた境内の
緑が一杯で隅々まで行き届いた爽やかさは、
上品で女性的でさえあった。
|
|
室生寺:奈良時代後期(770〜780)勅命により興福寺の僧賢憬が創建し、室生寺は奈良仏教界の山林修行の霊地となった。
その後平安初期に弟子の修円が伽藍などの造営を行い、真言、天台密教の道場として栄えた。江戸中期になって興福寺の支配からはなれ、現在は真言宗室生派の大本山となつている。
鎌倉時代以降は同じ真言密教の高野山の女人禁制に対し、室生寺が女性に門戸を開いたことから、「女人高野」と呼ばれ広く親しまれている。また平安京の都から遠い位置にあったので破壊焼失からの災難をまぬがれ、仏教美術品を多数所有する貴重な寺院となっている。
なお五重塔は平成10年9月の台風で大きな損傷を受けたが、平成12年に修復が完成している。
季節になると境内に一面に咲く石楠花(4月下旬から5月初旬)と紅葉の美しさは特に有名である。
|
|
|
|
京都駅を出発し近鉄室生口大野駅に着くと外は小雨で、高台にある駅舎からは下に駅前広場が見える。
前方遠くには雨にけむる山並(写真右)が見えるが、その方向に室生寺がある。
広場に行くとバスが数台並んでいたが、時間帯が悪く室生寺行きは1時間に1本のみで断念した。
タクシーで運転手の地元言葉と早口でよく分らないガイドを聞きながら、約7kmの道のりを急いだ。
|
|
|
室生村へ近づくと前方に室生川の上流にかかる朱色の橋(写真左)が見えてきた。
当日は月曜日でかつ雨ということもあってか、観光客の姿は殆ど見られず
ひっそりとした門前町(写真中)を貸切観光気分で中ごろまでくると
左手に先ほど見えた太鼓橋が、雨の中で鮮やかな朱色を見せていた。
|
|
|
太鼓橋を渡ると正面に表門(写真左)があり、右に「女人高野室生寺」の大きな石碑が立っている。
ところでとかく寺院では女人禁制などと、女性を差別したりすることが多いようであるが、
そういう差別をする男たちは、誰から生まれたと思っているのだろうか。
それに余談ながら、戒名などで死後も差別しているが
こういういろいろな差別をすることがお釈迦さまの教えだと思っているのだろうか。
本当にバカらしく、情けない!
表門から右折すると続いて左側に赤門(写真中)があるが、多分これは護摩堂の入口であろう。
もとは赤く塗られた門の証に、扉にはかすかに朱色が残っていた。
さらに進むと両側に仁王像を構えた大きな仁王門が建っている。
室生寺は階段の多いところであるが、仁王門から奥の院までは約700段の階段が続く。
|
|
|
仁王門を入ると、右側に受付があるので、拝観料500円を払う。
受付を過ぎると、前面の高くなったところに、広い休憩所と大きくてきれいなトイレ設備が整っている.
この設備を見ただけでもいかに女性を大切にしてきた寺院か、ということが遠慮なく伝わってくる。
右折して少し歩くと左側に、紅葉がとても美しいというばん字池(写真左)がある。
ばん字池から左折して、両側が石楠花で飾られた鎧坂と呼ばれている石段を登る。
|
|
|
階段を登りきると3面が杉木立に囲まれた広場に出る。
広場の正面には金堂(写真中),左側には弥勒堂(写真左)、右側には小さな天神社(写真右)が建っている。
平安初期に建てられた金堂(国宝)は、前面に礼拝のための階段がなく回廊からの礼拝となっている。
これは、江戸時代に礼拝階段を撤去して前面に堂を張り出して増設したためであり、
またそのため写真のように、屋根も前面に増設したような形となっていることがわかる。
礼拝所からは、金堂の中に平安初期の238cmの一本木造の本尊、釈迦如来立像(国宝)や
薬師如来像、地蔵菩薩像(平安初期、重文)、文殊菩薩像(平安初期、重文)
十一面観音菩薩像(平安初期、国宝)、十二神将像(鎌倉時代、重文)が安置され、
また本尊の背後の板壁には、帝釈天曼陀羅図(平安初期、国宝)が画かれているのがよく拝見できる。
弥勒堂(重文)は興福寺の伝法院を受け継いだとされる鎌倉時代の建築で、
本尊の平安初期の弥勒菩薩立像(重文)と客仏の釈迦如来坐像(平安初期、国宝)が安置されている。
天神社は、室生寺が創建されたとき既にあった室生龍穴神社に敬意を表して
その方向に祠が建てられている。
この祠の両側の杉の木立から差し込む朝日は、神々しくまた神秘的であるという。
|
 |
金堂の左側の石段を登るとそこには本堂の灌頂堂(国宝)が見える。
鎌倉時代の延慶元年(1308)年建立で、真言密教の最も大切な法儀である灌頂を行うところである。
本尊は平安中期の作で、日本3如意輪のひとつといわれる如意輪観音(重文)が安置されている。
|
|
|
本堂の左側の急な石段を登っていくと、正面に五重塔(国宝)が見えてくる。
塔の建立は平安時代より古い天平時代といわれ、室生山中で最古の建築物である。
総高16.1mで屋外に建つ五重塔では最小といわれ
朱と白の鮮やかなコントラストは荘厳ではあるが、とても優美さを感じさせる建築である。
平成10年9月の台風7号の倒木で大きな被害を受けたが、平成12年10月に修復が完成している。
当時被害を与えた倒木を思われる杉の木の残骸が、
左側に並んでいるお地蔵さまの裏側に放置されていたが、まだ処分できていないのであろうか?
|
|
|
五重塔の左のゆるい階段(写真左)から奥の院へ向かう。
階段を登りきると巨木の中の平坦な山道が続くが、小雨にけむるさまはまさに神秘的でもあった。
しばらくすると前方に朱色の小さな橋が見えてくる。
|
 |
橋を渡ると右手に奥の院に延々と続く急勾配の石段がある。
この400段余りの石段は、確かに息が荒くなり一気の登ることはできなかった。
昔参拝にくる女性にとっては、室生寺は決して生やさしいものではなかったはずである。
|
|
|
ようやく階段を登りきると小さな広場になっていて、正面に仮設のような社務所があり
その左側に奥の院御影堂(写真右)、登ってすぐ左にはに工事中の位牌堂がある。
鎌倉時代に建立された御影堂(重文)には、弘法大師42才の像が安置されている。
位牌堂は舞台つくりとなっていて、そこからは雨でくもる室生町の全景を見下すことができた。
|
 |
奥の院からの戻り、今登ってきた石段を上から見てその険しさを改めて認識してしまった。
|
|
|
受付まで戻ってきて、そこから赤門、表門の内側に立ち寄ると
そこは石楠花の園で、シーズンともなるとさぞかし美しいことだろと思う。
その石楠花に囲まれて右手には護摩堂(写真右)、奥の正面には本坊の建物がある。 |
| |
|
|
| そして表門から、室生川にかかる太鼓橋を眺めるとまた趣のことなる景色があらわれた。 |
| |
室生口大野駅まで7kmを歩く予定で、小雨の中を周りの景色を堪能しながら歩いていたら、
後から来たバスが追い抜き、突然停留所でもないのに前方で停まってしまった。
さてはと思い、バスまで早足でたどりついたらドアーを開いてまっていてくれたのでした。
バスには乗客ゼロで道中も乗客なし。
運転手さんと仲良く駅に向かいました。 |
| |

|
| |
| |
| |