|
|
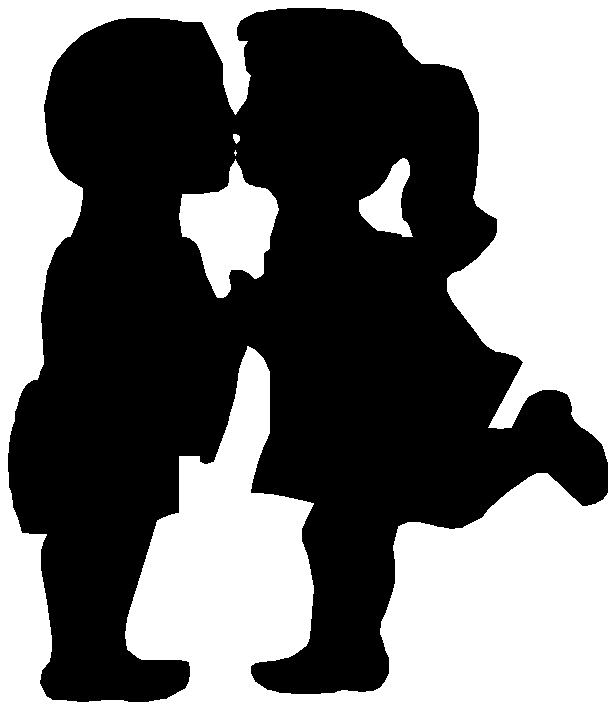 |
お吉哀し
下田の港 |
| iー愛ロマンチカ |
|
| |
伊豆半島の先端に位置する下田市を2005.1.26~29と2.13,14に2回訪れた。
|
下田は、1854年(安政元年)アメリカ海軍ペリ-提督の率いる黒船の再来で幕府が開港し、
また1856年(安政3)米国使節タウンゼント・ハリスが、わが国最初の領事館を置いたことで知られている。
そして開港に係る重要な史蹟、資料やエピソードが多くあるが、
私は、わずか17歳の身で「お国のために人柱になれ」いわれハリスに人身御供として差し出され、
それでもけなげに条約交渉が日本に有利になるように一生懸命ハリスに奉仕し、
日本開国の重要な役割を果たした、お吉をおもんばかり、涙を流す。
それなのに町の人たちからはヤシャメン(洋妾)とさげすまれ、「唐人」と冷たい仕打ちをされて、
ついには豪雨の日の夜に川に身を投げさざるを得なかったお吉を悲しく哀れに思う。
そのうえお吉の誰も拾ってくれない亡骸を宝福寺の住職が埋葬してあげたら、
その住職まで非難され結局町から追い出してしまうなどと聞くと、
人間(日本人?)のエゴと残忍さ、それに宗教とは何なんだろうと、改めて考えさせる。
本当にこんなことがあってよいものかと思うが、
よく考えて見ると同じようなことが今日でも日常おきていることのような気がしてならない。
私にとっては、下田はお吉の町である。
|
 |
|
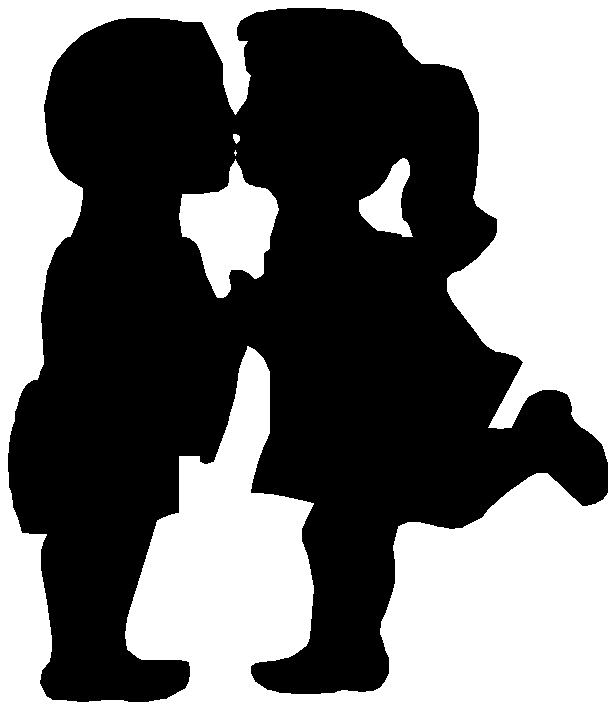 |
| ① お吉コース |
 |
伊豆急電車で伊豆急下田駅に到着。
|
|
|
駅舎南側の出札口(写真右)を出ると、駅前広場の大きな黒舟が出迎えてくれる。
|
|
|
広場を直進し135号線を横断して駅前橋商店街に入ると、左側に香煎塚の祠がある。
喉を病んだ人や唄の上手になりたい人がお茶をもって願掛けにくるという。
|
|
|
商店街を過ぎ通りを横断し路地を出ると右手に、1466年(文正元)創立の稲田寺がある。
山門を入った左手には鶴松の墓案内板があり、5m先に墓がある。
納骨瓶には、俗名大工川井又五郎明治9年6月6日没、と記されているという。(鶴松は幼名)
許婚のお吉を領事ハリスの侍妾として差し出され、仲をさかれた鶴松は哀れな一生であった。
ハリスと別れた後のお吉と4年同棲したが故あって離婚し、その翌年死亡している。
お吉は鶴松の大好きだった山桃を墓前に供え、泣きながら冥福を祈ったという。
またこの墓地には安政の東海地震の大津波で犠牲になった人たちを供養する津波塚がある。
山門右手の阿弥陀堂には、平安時代後期の像高208cmの大きな阿弥陀如来坐像(下田指定文化財)が、
観音・勢至菩薩を両脇に従え安置されている。
|
|
|
メインストリートのマイマイ通り(写真右中)に出て右折して南へ向かうと、
道の反対側に下田御陣屋跡碑と並んで春水の松(写真左中)がある。
ここは明治29年に医業を営む傍ら、小説「唐人お吉」書きお吉を世に紹介した村松春水の屋敷跡で
この松はそのときの庭木である。
マイマイとは、カタツムリからきた名で、ペリー来航でこのマイマイが日本に上陸したと考えられている。
道の右手には、豆州41番の霊跡の海善寺がある。
|
|
|
その先の右側に、大きな唐人お吉記念館看板が立っている宝福寺がある。
1559年(永禄2)開基の宝福寺は、
1854年(嘉永7)締結の日米和親条約で下田開港の時に下田仮奉行所となった。
墓地には「下田年中行事」を書いた平井半次郎や、お吉の墓がある。
白い看板を潜ると、左側に本堂、右側に記念館(入場料300円)と墓がある。
本堂の前には「幕末下田奉行所跡」看板(写真左)が掲げられ、
堂内には多くの椅子とテーブルが置かれ、いかにも当時異国人との交渉場所であった跡が伺える。
|
|
|
右側の平屋の記念館に入ると、お吉に関する資料が多数展示されていて音声による説明もある。
中でも生前のお吉を偲ぶ写真や人形には、心が傷む。
19才のお吉の実物写真(写真左)は、これほどの美人はかってこの世にいたであろうかと思う。
お吉は本名を「斉藤きち」といい、1837年(天保12)愛知県知多郡内海で生まれ、
4才の時家族と一緒に下田に移り住んだ。
学問、技芸の道を学び14才で芸妓になり、新内明烏のお吉とうたわれるほど評判の美人であった。
1856年(安政3)、初代総領事ハリスが日米通商条約締結のため下田の玉泉寺に領事館を置いた。
ハリスが町内を見分中、浴場(当時は混浴)にいる裸のお吉に目がとまった。
通訳ヒューストンの要請で、初めての領事館の対応に腐心していた奉行所は、
お吉をハリス、お福をヒューストンの侍妾にすることに一決した。
鶴松という許婚がいて拒否するお吉を、下田奉行所支配頭取伊差新次郎の「お国のために人柱になれ」
の言葉でいやいや大役を引き受け、ハリスの下へ侍妾として差し出されることになった。
「ヤシャメン」、「唐人」などとの罵声を浴びながら、駕籠で領事館に通い、
日本外交が有利になるようにハリスに献身したことにより、1858年(安政5)に通商条約が締結に至った。
その後町を逃れ幕末動乱に京都祇園の芸妓となり松浦武四郎の片腕として開港に奔走したりしたが、
1868年(明治元)25歳の時横浜で鶴松と再会して同棲し、再度1872年下田に戻り髪結い業を始めた。
ただ町の人の罵声や冷たい目に耐えられず、深酒をするようになり4年で鶴松と別れ、
三島の芸妓に出たりしたが、1882年42才で下田に戻り小料理屋「安直楼」を開業した。
しかし酒に身をやつし店は破産し、
「唐人」となどと世間の罵声と嘲笑を浴びながら貧困の中に身をもちくずし、
明治24年3月25日の豪雨の夜下田蓮台寺の稲生沢川の淵に身を投げ、波瀾にみちた生涯を閉じた。
わずか51年の哀しくもはかない終焉であった。
「お国のため」と言われて身をささげたお吉に、何の罪があったのであろうか、
そしてお吉にとって、何が「お国のため」であったのであろうか。
なおハリスは1862年(文久2)に帰米し、1878年(明治11)に死亡している。
髭だらけのタウンゼント・ハりスの写真(本当は掲載したくなかったのですが)→ |

|
|
|
|
お吉には身寄りがなく、また触れるとけがれるなどといって亡骸は放置されたままであった。
宝福寺の第15代竹岡大乗住職が、慈愛の心より法名「釈貞観尼」を贈り境内に手厚く葬った。
そのお吉の墓が記念館の裏の片隅にひっそりとたたずんでいる。
ところが、町の人はこれが悪いと、ついには住職を寺から追い出してしまうのであった。
ここまでくると、人間とは本当に残忍で恐ろしい動物だと思う。
明治時代に、お上の達しということで、
今まで信じていた仏像の首を平気でちょん切ったり破壊した日本人に共通する何かのようなが気がする。
なお昭和5年に水谷八重子らの寄進により、この墓の左よりのところに新しい墓が建てられている。
|
|
|
マイマイ通り(写真右)に出て右折して進み、
交差点の左側の立派ななまこ壁の建物のところで左折して大横町通りを進む。
|
 |
商店街を200mほど進だ交差点を右折すると、安直楼の暖簾のある建物がひっそりたたずんでいる。
お吉が三島から1882年(明治15年)下田に戻り開業した小料理屋「安直楼」は2年で廃業した。
その後他人に渡り寿司店となり開業していたが、現在は下田市歴史構造物に指定され公開されている。
2階には当時の客間と遺品がそのまま保存されている。入場料200円。 |
| |
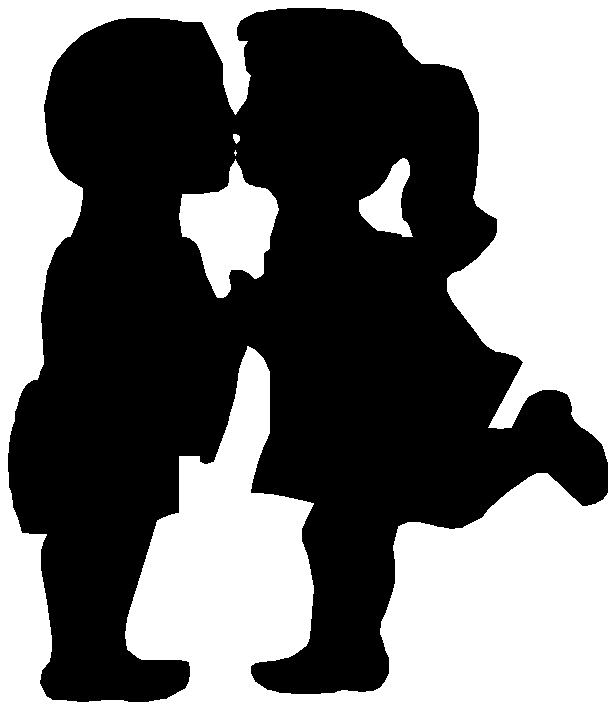 |
| ② 和歌の浦遊歩道コース |
|
|
マイマイ通りの突き当たりにある了仙寺は、国指定史跡となている。
1854年横浜で締結した日米和親条約の細部を決めるため、
下田に上陸したペリーは了仙寺で林大学頭日本側全権と1854年6月(嘉永7)に日米下田条約を締結した。
この中で、アメリカ人は下田の街中を自由に歩く権利を与えられ、
ここで黒船のアメリカ人と下田の町民たちの異文化の交流が始まった。
また下田の町民たちを対象にコンサートがアメリカ海軍の軍楽隊によって開かれたが、
これが日本で最初の洋楽のコンサートと言われている。
なお日米和親条約では、下田と箱館(凾館)の開港(箱館は翌年に開港)と、
アメリカ船の日本における物資の確保およびアメリカ人の安全の保障などが決まった。
境内は4月から5月にかけて1000株のアメリカジャスミンの香りで包まれるという。
寺の背後には、人骨、玉類、金銅製腕輪や耳飾、須恵器土師器などが出土した洞窟古墳がある。
併設の黒船美術館には、黒船、ペリー、開国、異文化交流をテーマとした
1000点を超えるコレクションがある。
館内には男にも女にも共通の、こよなく思いがけない陳列品もあるのでした。
|
|
|
了仙寺を出て右折して進み、
ナメコ壁建物のある十字路でペリーロードへの道標が立っている道へ右折する。
|
|
|
進んで行き平滑川にかかる霊山橋の手前で左折した道がペリーロード(写真中)となる。
黒船でやってきたペリー提督が行進した道で、なんとなくオシャレさを感じさせる。
その先の朱色の柳橋を渡る。
|
|
|
ゆるい坂道を登って行くと右手に長楽寺がある。
1854年(安政元年)この寺で日露和親条約が締結され、国境が定められた。
択捉と得撫島の間に境界を置き、択捉、国後、歯舞、色丹は日本領土に、
得撫島以北の千島列島はロシアに属す。
樺太は日露両国人の独居を認めることになった。
何か重要な歴史を学んだような気になり、いつか道も下り坂となると
正面に相模灘の大浦が見え、丁字路となる。
右折して湾沿いの道を行くと、下田御番所跡、さらにその先には有馬稲子の住宅があるはずだが
地元の人に聞いても有馬稲子の名前さえ知らなかった。時は過ぎたり!
|
|
|
左折し半島を周る約2kmの和歌の浦遊歩道(写真右)を歩く。
道は左へカーブし大浦、志太ヶ浦と海岸の景観を堪能する。
|
|
|
半島の先端の赤根島の取り付け部辺りに、ドーム状建築物の下田海中水族館が姿を現す。
入口に付近には、大きな亀のいる水槽があり、ご挨拶するととても恐い顔。
それでも精一杯手を振って愛嬌を示めしているのでした。(私の勝手な推測ですが)
|
|
|
水族館を過ぎると、遊歩道の名前はベイサイドプロムナードとなり和歌の浦の景観を楽しむ。
手前の島は雁島で右奥の島は犬走島。
|
 |
雁島へは吊り橋で渡る。
島はとても狭いが確か一週して周囲の景色を楽しむことが出来る。
|
|
|
犬走島へは魚釣人で賑わう突堤を延々と歩いて渡り、岩と岩の間にあるトンネルを潜ると
そこには真っ白な灯台が現われる。
|
 |
さらに進んで行くと朱色の鳥居がとても似合う、みさご島(遊覧船黒船サスケハナから撮影)。
|
 |
遠くには下田港と寝姿山をバックにした、下田温泉ホテル群。
|
 |
遊歩道が終わりに近づくと、右側にペリー胸像のあるペリー艦隊上陸の碑がある。
1854年(嘉永7)締結の日米和親条約で開港地として下田港が提示されると、ペリーは調査船を派遣した。
下田港は外洋と接近し安全に容易に近づけること、船の出入りに便利なことなど、
要求項目を完全に満たし港であった。
即時開港となった下田にペリー艦隊が次々と入港し、艦隊の乗組員が上陸したのが、
この下田公園下の鼻黒の地であった。 |
| |
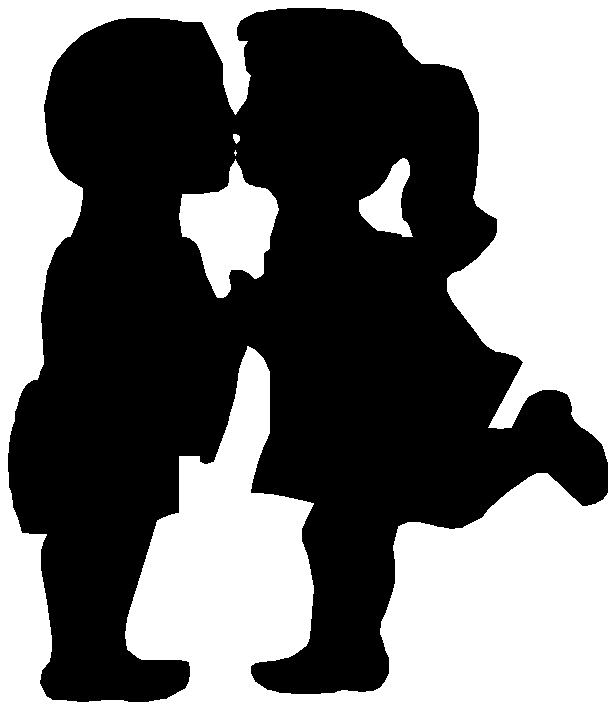 |
| ③ 稲生沢川西河畔コース |
 |
伊豆急下田駅を出て、135号線を寝姿山へ向かい東へ進む。
|
|
|
東急ストアーを過ぎた辺りから、右側の運河の脇の細い道をななめに入り川沿いに歩く。、
左斜め後ろを振り返ると新下田橋の欄干が見える。
|
|
|
稲生沢川にかかるみなと橋のところで右折し、2つ目の交差点を左折すと
左側にいろいろな観光案内図によく紹介されているなまこ壁の建物(写真左)がある。
なんとなく歴史的な雰囲気を感じさせるが、
他にも古そうななまこ壁の建物が多々あり、何故この建物だけが紹介の対象となっているのか不明。
|
|
|
なまこ壁の建物から右折して、最初の交差点を左折した通りを南へ進み
2丁目11-10の中央商店街の駐車場脇に「ハリスの足湯」ピンク看板で飾られ建物がある。
入湯は無料とさすが温泉地と思ったら、ちょっと先に若き女性の二人蓮れが入ってしまった。
女性に縁の無い私は、またの機会にしよう。
|
|
|
先に進み十字路で左折する。
弁天橋の前方(写真右)はベイサイドプロムナード道路となり、ちょっと先にペリー艦隊上陸の碑がある。
弁天橋手前から左折して、前方に漁船や寝姿山を見ながら狭い護岸の道を進む。
|
 |
しばらく歩くと、左側に鳥居のある五六七(ミロクと呼ぶ)稲荷ある。
この地がまだ葦の生茂る湿地帯のころから鎮座している江戸時代からの古社で、
海上安全・家内安全祈願として崇敬を集めたいたという。
|
|
|
| 広い船着場の通りを歩くと、前方右手に寝姿山と新下田橋が見えてくる。 |
| |
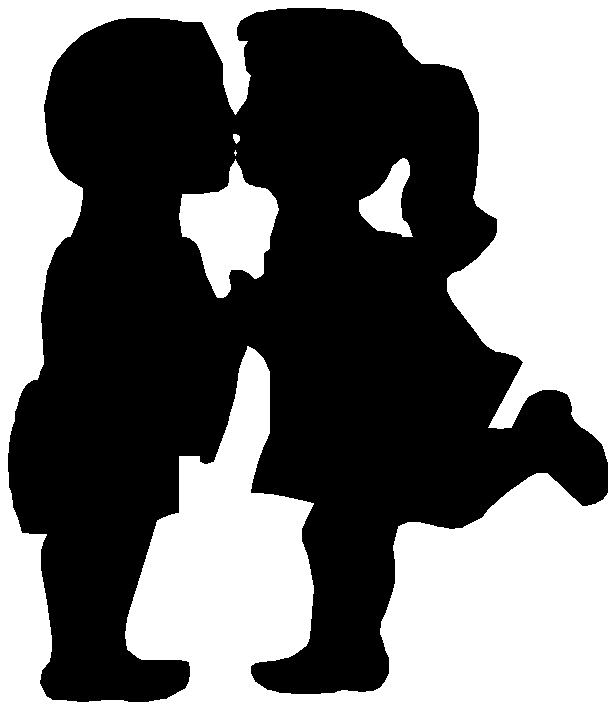 |
| ④下田港→白浜コース |
 |
135号線の新下田橋を渡る。
前後の欄干に裸婦像が4箇所ある芸術的な橋である。
|
|
|
橋を渡り振り返ると一段と魅力的な裸婦像で、私はこの像がお気に入り。
橋から穏やかな稲生沢川を眺める。
この上流でお吉が身を投げたのであった。
|
 |
新下田橋から西へ約1km進むと、135号線に面して約3万㎡のまどが海浜公園がある。
よく整備された公園で、芝生や遊歩道などがあり天気がよい日は港を眺めながら一日過ごすのもよい。
|
|
|
黒船ホテルから撮った港内写真(写真中)で、
手前が海浜公園、右の埠頭が遊覧船乗り場、左がみさご島で右奧が犬走島、その中間が黒船投錨地。
遠くに見えるのが須崎半島で先端に野生の水仙群で有名な爪木崎がある。
公園には、巨大な碇と西条八十の歌碑(駕籠で行くのはお吉ぢゃないかb下田港の春の雨 泣けば椿の花がちる)
|
|
|
近くで見る遊覧船黒船「サスケハナ」はとても大きいが、
実際に来航した黒船はこの船より長さで20倍、トン数で40倍あったという。
確かに太平洋を延々と渡ってくるわけだから、軍艦としてはそれでも小さいくらいなのであろう。
黒船で港内を一周すると、近く遠くカモメが寄ってくる。
所要時間約20分、大人920円
|
 |
公園の前の黒船ホテル7階の露天風呂からは、何か南洋気分で下田港を堪能できる。
|
|
|
135号線を歩いて約3km先の白浜へ向かう。
まどが公園を過ぎると須崎半島の付け根となり、
そこにはハリスが望郷の思いにかられながら散策したという、海岸沿いのハリスの小径や、
1856年初めてアメリカ総領事館を設置した玉泉寺がある。
右側に広がる港内を眺めながら坂道を登って進む。
|
 |
歩道もきれいに整備されている区間もある。
|
|
|
坂道を上り切ったあたりに、小さなフェニックス広場があり「交通安全 誓乃像」がある。
|
|
|
道は下り坂となり、しばらく行った小さな見晴広場に、与謝野鉄幹・晶子の歌碑がある。
詳細は失念したが、そこから見える岩に砕ける荒波の白さ、を歌ったものだったと思う。
確かに白い波の砕けるさまは印象的である。
|
|
|
坂道を下り平坦になると右側は白浜海岸となるが、この日は天候のせいか白い浜とはいえない状態。
白浜の中央くらいのところに、ビーチバレー発祥の地碑が建っている。
日本での発祥なのだろうか、それとも世界での発祥?
いずれにしても思いがけなところにあるものである。
|
|
|
白浜海岸の先に、135号線に面して古木に囲まれた伊豆一の宮で神話をもった白浜神社がある。
2300有余年の歴史を有する由緒ある神社で、境内には国指定天然記念物の「あおぎり」自生地や、
県指定天然記念物「柏槙(びゃくしん)」樹林がある。
ご神木白龍の柏槙(写真左)は、枯れてから1300年たつという超巨木である。 |
| |
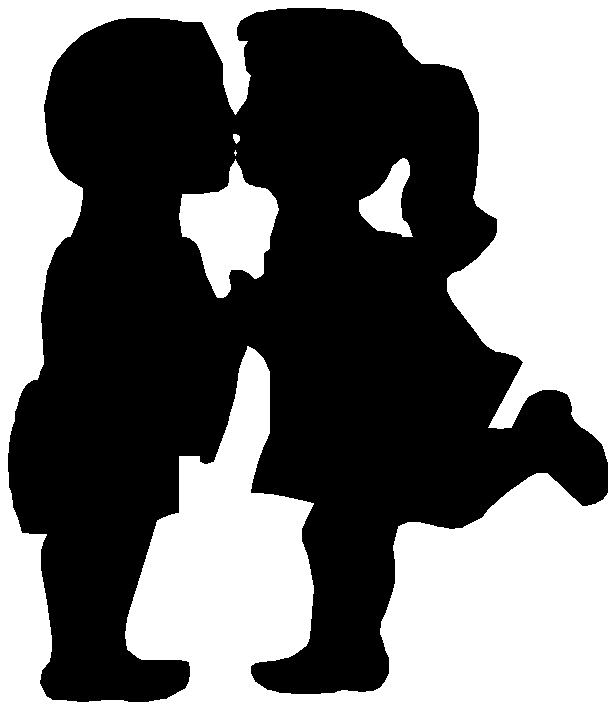 |
| ⑤寝姿山山頂コース |
 |
駅舎の東側にある伊豆急下田駅入口。
|
|
|
駅前正面には、温泉のご当地よろしく温泉のデモンストレーション(写真中)。
左側には、屋根に時計のついた大正時代の洋館を思わせる食堂。
その先の正面に、寝姿山をバックにした寝姿山ロープウエーの大きな看板。
|
|
|
駅から歩いて数分で、ロープウエー乗り場に到着。
往復料金1000円
ちなみに寝姿山頂上に行く道がないため、このロープウエーが唯一の交通手段。
|
|
|
海抜200mの寝姿山頂上までの約3分間、下界の景色を楽しみながら到着すると、
富士箱根伊豆国立公園寝姿山自然公園案内標識が迎えてくれる。
下田市街から見ると女性の寝姿に似ているところから、寝姿山と呼ばれているという。
私もその気になって見たが、悲しいことに女性の寝姿を見たことがないため想像できないのでした。
|
 |
頂上は一周する散策路が整備され、よく手入れされた自然公園が快い。
この時期咲いている花、はな、花
|
|
|
 |
展望台からは、遠くは伊豆七島、爪木崎、美しい山並みの天城連山などの雄大な景観。
眼下には下田の港の素晴らしい光景。
|
|
|
この頂上では、ひと際色鮮やかな愛染明王堂。
奈良法隆寺の夢殿を3分の2の大きさに再現したもので、
中の本尊「愛染明王」は元鎌倉八幡宮愛染堂の本尊で、仏師運慶の作と言われている。
堂の左の斜面には、平安時代の作といわれる150余体の寝姿地蔵が人々の幸せを祈っている。
|
|
|
 |
戻りの散策路。
|
|
|
お花畑にお似合いでない、黒船見張所看板と港を睨む巨大な黒光り大砲。
1849年(嘉永2)4月12日英国測量船マリナ号の入港を機に、幕府がこの寝姿山山頂に見張所を設け
下田奉行所より数名派遣して日夜黒船警戒に当たらせた。
見張所の看板は、当時の面影を偲ぶために復元したものといい、
大砲はその米国船に当時搭載されていたもの、とのこと。
勇ましく、黒船を狙って備えた日本の大砲ではなかったんですね。
それにしても、この黒光りする大砲は凄さがあります。
当時の人が黒船を恐れおののいた気持ち、分ります。 |
| |
| 私には、どうしてもお吉が哀れでしょうがない。 |
 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |