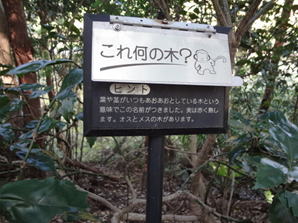|
| 2021年1月15日 |
|
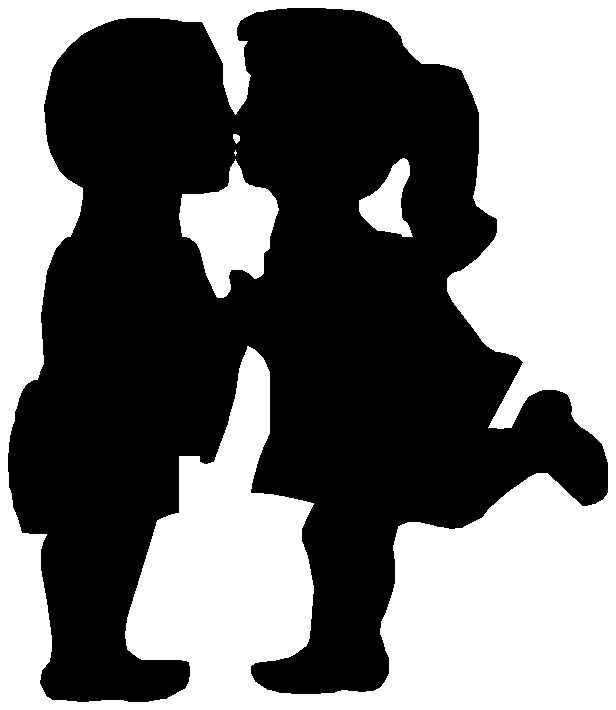 |
一駅読み切り |
| (神奈川県)相模鉄道沿線・半径1kmの駅 |
|
|
| 相鉄本線「相模大塚駅」 所在地:大和市桜森3丁目 |
| 開業:1926年(大正15) 一日平均乗降客: 約11,400人(2020年)、約14,300人(2019年度) |
| 駅間距離:大和駅から 約1.9km |
| 駅名由来 |
| 開業当時の駅は現在の「さがみの駅」付近にあり、近くに「おおきな塚」があったことから駅名の由来となった。 |
| その後、駅舎は現在の桜森に移転した。 |
| 駅舎 |
| 1975年(昭和50)に、現在の橋上駅舎となった。 |
| |
| この駅には、2020.11.18に訪れた。 |
| ここでは、大和駅で訪れた「ふれあいの森」に隣接している「泉の森」を散策した。 |
| 経路 |
| 相模大塚駅北口→ 「泉の森」→ 北口 |
| 歩行距離:往復約 1.2km + 泉の森公園内散策 約2km |
|
| 泉の森:引地川の水源を中心に、国道246号を挟んで約42ヘクタールの広さの自然を核とした公園。 |
| この地一帯はかって引地川沿いの谷戸田であったが都市化で雨量が多くなり、洪水が発生するようになったため、 |
| 1982年(昭和57年)上草柳調整池を整備し、また公園として開放した。 |
| 樹林地と水辺が特色ある生態系を形成し、約900種の植物約50種の野鳥などの生き物が生息しやすい環境となっている。 |
| 主な見どころは、郷土民家園、森のはらっぱ、湿性植物園、緑のかけ橋、水車小屋、しらかしの池 など。 |
|
| 泉の森公園散策経路 |
 |
| |
| 泉の公園へ |
 |
 |
 |
| 相模大塚駅南口 |
北口の正面の道を進み、「相模大塚駅北口」信号に出て右斜めの道に入る。
|
 |
 |
 |
| まっすぐな道を進み「いなりや」角の交差点を左折し、その先の信号交差点を直進する。 |
| なお、この信号交差点には泉公園からの帰りに戻ってくる。 |
道なりに進み「泉の森駐車場」看板の立つ公園に入る。
|
 |
 |
 |
| 駐車場の右奥から細い下り道を道なりに進み、「大和市郷土民家園」看板の立つ入口に入り、 |
| 消毒液ビンの置かれている門を潜る |
| |
| 旧小川家主屋 |
| 江戸時代中期に建てられた大和市最古の民家。昭和59年に上和田からこの地へ解体移築された。 |
 |
 |
 |
| 寄棟造り主屋 |
| この時コロナの真っ最中。絶対に建屋内には入れさせないぞ!と、体を張る案山子君。 |
| 大戸口から恐る恐る中を拝見。ピッカピッカに光る板の間! |
| |
| 旧北島家主屋 |
| 江戸時代末期に建てられた代表的な養蚕民家。昭和61年に下鶴間から解体移築したもの。 |
 |
 |
 |
| 紅葉の木々の間の奥に、主屋。 |
| 入母屋造りで、屋根裏を蚕室にしている。 |
ここも立ち入り厳禁で、大戸口から中をのぞくと土間の向こうにピッカピッカの板の間。
|
 |
 |
 |
園を出て左折し、右にカーブした先の(目立たない)階段上り口から、急で長い階段を上り、いよいよ森の中に入る。
|
 |
 |
 |
| 落葉の道を進むと、右側に「木製遊具」。その脇で、幼稚園生が先生の話を熱心に聞いています。 |
| その先左手に、樹林に囲まれた「ふれあいキャンプ場」。 |
道なき道を踏み分けて行き、交差点らしき形跡のところを右折する。
|
 |
 |
 |
森の中を進み、交差点を横断し、「くぬぎの森」の中を歩く。
|
 |
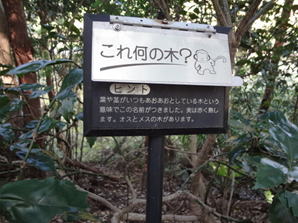 |
 |
| 「ハチにご注意ください」標識。気配はないけど、油断なく注意しますね。 |
| 「これ何の木?」掲示板。これからもあちこちに立っていますが、恥ずかしながら私は全くの植物音痴。 |
| ただその下にいろいろヒントや解答が書いてありますので、恥をかかずにすみます。 |
しばらく進み急階段を下りて左折する。
|
 |
 |
 |
| その先で国道246号線高架下を潜り、道なりに進み、右手下に「野鳥観察デッキ」。 |
| 目の前にある大池に飛来してくる、シジュウカラ、メジロ、ヤマガラ、エナガ、カワセミ、コゲラ、アオサギなどの観察場。 |
ちなみに、泉の森では50種類以上の野鳥をも観察できるという。
|
 |
 |
 |
| 目の前にあるという大池を探すけれど、木々に紛れて私には全く不明。 |
| 諦めて山道を進むと、見つけました!右下方に幻想的な大池を。 |
| |
| 「森のはらっぱ」へ |
 |
 |
 |
| その先の丁字路に、「山野草の小径」道標。 |
| 「森のはらっぱ」へ行くには、このまま「アセビの道」を通るコースと、右折して「山野草の小径」を通るコースがある。 |
| 両方歩いてみたが、山野草のコースの方が適度なアップダウンが快くまた景色も変化に富み距離も短く、お勧めコース。 |
| ここでは「山野草の小径」に入る。 |
丁字路を右折して坂道を下り、「かしゃぱやま林間広場」脇を通り、柵沿いに軽いアップダウンを繰り返して進む。
|
 |
 |
 |
こんなところも通り、急な坂道を下ると板道となり、その先の「山野草の小径」道標の立つ交差点を横断する。
なお、この交差点で左手から下ってくる「アセビの道」コースと合流する。
|
 |
 |
 |
| 細い道を進み、突当りに「森のはらっぱ」(合成写真)。 |
| 「森のはらっぱ」案内板(要約):現状は木が成長したため、「はらっぱ」の姿ではなくなってきているので、 |
| 数年かけて木を間引いてゆっくりと草原を再生し、いろいろな生物が生息する豊かな環境を作ることを目指している。 |
| 切り株の残るはらっぱをU字型に一周する。 |
| |
| 引地川源水へ |
 |
 |
 |
| はらっぱの反対側の板道を通り、車道を横断して森の中の道を道なりに下り続け、 |
| 右側に「大和水源」立看板。しっかり門は閉じられ、立入厳禁。 |
| 大和水源:大池と小池と呼ばれる2つの池があり、池の底から水が湧き出ていて、水源地周囲の樹林は水源涵養材として保護。 |
| この湧き出た水が引地川となり、相模湾まで流れる。 |
| |
 |
 |
 |
| 引地川水源に近づくために、門のすぐ先で右手の林の中に入り落葉の坂道を下る。 |
| ベンチが多数な並ぶ「野外教室広場」の中を通り、突当りの丁字路を右折して道なりに下る。 |
| |
 |
 |
 |
| 下り切ったところで小さな川にかかる板橋(写真中)を渡る。この川が引地川。 |
| 橋の右手(写真右)が上流で立入禁止柵。ここから約50mくらいのところが大和水源かな?(勝手な推測) |
下流を見ると、きれいな透明な流れ。上流と水の色が違うのは太陽の光のせい。
|
 |
 |
 |
| 橋を渡り、道なりに左にカーブし「せせらぎ広場」脇を進む。 |
左手に顔を出す引地川。ここから引地川沿いに進み、国道246号線高架下を潜り左にカーブする。
|
| 緑のかけ橋へ |
 |
 |
 |
| 右側にトイレの建物があるところで階段を上り、右折して進み坂道を上り、道なりに進んで「緑のかけ橋」入口に来る。 |
| 緑のかけ橋 |
| 緑のかけ橋:全長53m、幅2m。1991年(平成3)完工。ベイマツ集成材の木製斜張橋。 |
| 谷戸(丘陵地が浸食され形成された谷状の地形)の湿性植物園の上に東西にかけられた橋で、橋から園内を一望できる。 |
| 建設省主催の「手づくり郷土賞」を受賞、アメリカ木造協会木橋部会による「木造橋歩道橋部門」第1位受賞。 |
 |
 |
 |
広大な谷戸にかかる緑のかけ橋。橋の左手(北側)に水車小屋、右手に谷戸(南側)の遊歩道。
|
 |
 |
 |
| 入口に戻りすぐ左の階段から谷戸へ下りる。 |
| 「緑のかけ橋」下を潜り、「あそび小川」沿いに北へ向かい平成2年に造られた巨大な「大和の水車」。 |
| 大和で、水車を動力として杵臼で精米、精麦、製粉などが行われていた頃の名残。 |
| |
 |
 |
 |
| 谷戸の遊歩道を南に向かう。左折して湿性植物園(写真右)にかかる大きな木製デッキを渡る。 |
|
|
|
|
|
| 突当りを右折して川沿いの細い散策道を進み、その先で橋の袂に着く。 |
| 左折して橋を渡ると林の中の散策路へ。ここでは右折してちょっと散策。 |
|
| しらかしの池(上草柳調整池) |
| 草柳調整池:この地は、引地川に沿った谷戸田で稲作が行われていたが、流域の都市化が急速に進んだため、 |
| 雨水などの流入が多くなり水害が発生するようになった。 |
| そのため昭和57年に、治水地機能をもたせそして湿地の特性や周辺樹林地と一体となった上草柳調整池を造成した。 |
 |
 |
 |
「ふれあいステージ」とステージから見る「しらかしの池」。続いて「しらかし広場」。
|
|
|
| 広場の脇を通り坂道を上って左折したところに、展望デッキとそこから見る「しらかしの池」 |
| |
 |
 |
 |
| もとの橋の袂に戻り、散策道を進みその先で引地川と「しらかしの池に挟まれた道となる。 |
突当りで交差点に出て右折する。
|
 |
 |
 |
| なお引地川は、まっすぐ流れ直ぐ先で車道下のトンネルに入る。 |
| 歩道を進んで階段を上り、左折して土手道を進む。 |
| |
 |
 |
 |
突当りの車道を左折し、直ぐ先で「泉の森」看板の立つ横断歩道を渡り、階段を下りて引地川とシラカシ林の間の道を進む。
|
 |
 |
 |
| 突当りで引地川にかかる「ゆかり橋」を渡り、渡り切ってすぐ右折し、東名高速下のトンネルに入り「ふれあいの森」へ進む。 |
引地川も東名高速下のトンネルに入り「ふれあいの森」へ流れる。
|
 |
 |
 |
| 泉の森はここで終わり。さきほどの「泉の森」立看板の車道まで戻って左折する。ゆるい坂道を上り、信号を直進する。 |
| |
 |
 |
 |
| 来るときに通った次の信号を左折し、その先の「いなげや」角の交差点を右折して進み、 |
| 「相模大塚駅北口」信号を直進して相模大塚駅北口に着く。 |
| |