|
| 2020年10月15日 |
|
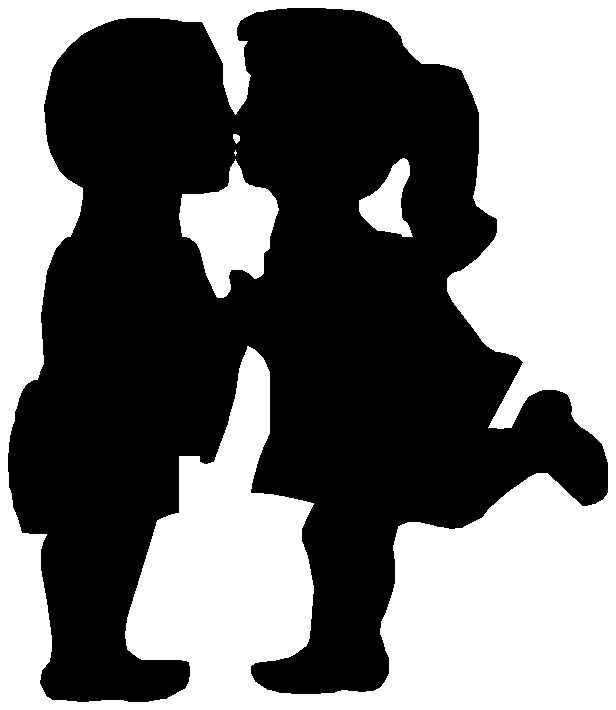 |
一駅読み切り . . |
| (神奈川県)相模鉄道沿線・半径1kmの駅 |
|
| |
| いずみ野線「いずみ中央駅」 所在地:横浜市泉区和泉中央南5丁目 |
| 開業:1990年(平成2) 一日平均乗降客: 約12,800人(2020年度)、約16,300人(2019年度) |
| 駅間距離:いずみ野駅から 約2.2km |
| |
| 駅名由来 |
| いずみの線が延長されて駅ができた時、周辺には泉区総合庁舎をはじめ公的な施設が集中し行政の中心的役割を担ていたので |
| 駅名も「いずみ中央駅」とつけられた。駅所在地の「和泉中央」という地名は、駅名から転じてつけられたもの。 |
| |
| この駅には、2021年9月21日に訪れた。 |
| ここでは、泉小次郎親衛の伝承の地、滝前不動尊、泉中央公園、長福寺、須賀神社、神明社を訪れた。 |
| 経路 |
| いずみ中央駅南口→ 滝前地蔵尊→ 泉中央公園→ 長福寺→ 須賀神社→ 神明社→ 駅北口 |
| 歩行距離 :約1.2km+園内400m。 |
| |
| 泉小次郎親衛(いずみこじろうちかひら):源満仲の弟・満快の子孫と伝えられる信濃源氏の出身。 |
| 鎌倉幕府が編纂した「吾妻鏡」が、泉小次郎を「剛勇の士」として紹介しているような、武勇優れた武士であった。 |
| 泉小次郎は、御家人として鎌倉幕府に仕えていたが、源頼朝の死後、執権・北条氏が実権を握る状況に我慢ならなかった。 |
| そして1203年(建仁3)北条氏が二代将軍・頼家を幽閉し、殺害するという事件が起きた。 |
| ここで、小次郎は頼家の遺児・千寿を擁し、北条氏を打つべくこの地に居城を築き計画を準備していたと言われる。 |
| しかし計画は1213年(健保元)に事前に発覚し、謀反に加わった御家人たちが次々と捕らえられた。 |
| 小次郎は、千寿とともに逃亡し諸国を渡り歩いた後、川越市の最明寺で千寿と一緒に出家し、 |
| 1265年(文永2)、80才の生涯を終えたと伝えられている。 |
| 泉中央公園:1986年(昭和61)に開園、和泉川東側の台地を整備して作られた公園で、面積約12千㎡。 |
| 伝承によると、ここには泉小次郎親衛の居城があったとされている。 |
| 城の遺構として、東側と南側に空堀と土塁が残っている。 |
| また、園内には、空充秋(そらみつあき)作の彫刻「門」がある。 |
| |
| いずみ中央駅(高架駅) |
 |
 |
 |
| 湘南台駅方面ホーム。 |
| ダメダメ、ダメよ! 待合室を覗いてはいけません。階段を下る。 |
| |
 |
 |
 |
| 階段を下りて右折し改札を出る。 |
| 出口から右折すると北口、ここでは左折して商店街の通路を進み、突当りでビルを出る。 |
| |
| 滝前不動尊へ |
 |
 |
 |
| 階段を下りて「メドウスいずみ中央」マンション前に出て右折し、その先の突当りを左折し、道なりに進む。 |
| |
 |
 |
 |
| 突当りは左斜めに折れ、右折して相鉄線高架沿いに進む。 |
| すぐ先右側の、「黒色の民家」と「サウスパレス」の間を入った民家の敷地と思われる奥に、朱色の鳥居。 |
| |
| 滝前不動尊 |
 |
 |
 |
| 平成23年12月建立の鳥居の前に、「横浜地域史跡 泉小次郎伝承地 ー滝前不動尊ー」白標柱。 |
| 鳥居を潜ると、祠の中に小さな仏像。 |
祠の右手の参道階段の上に、鬱蒼とした竹林の生茂る崖の前にお堂。
|
| 堂内には、不動尊と「和泉小次郎親衛守尊」と書かれた石塔が納められている、とのこと。 |
| ちょっと疑問:不動尊(=不動明王)は仏教であるのに、何故神社の鳥居があるのだろう。神仏習合を思えば、それもよし? |
| 滝前不動尊:泉小次郎親衛の守尊である不動滝があったところで、泉小次郎は戦いで流した血を滝水で洗ったとの言い伝え。 |
| 不動滝は、男滝(高さ1.7m、巾0.1m)と女滝(高さ2.0m、巾0.1m)があったということであるが、 |
| 現在は、名前の由来となった滝は周辺の宅地化などで、消滅しているとのこと。 |
| |
| いずみ中央公園へ |
 |
 |
 |
| 元の道に戻り、すぐ先で左折して相鉄線高架下潜り、一直線の道を進み、突当りを左折する、 |
| |
 |
 |
 |
| 20mほど先で右折して和泉川にかかる中村橋を渡る。中村橋から見る、整備された和泉川。 |
| 橋を渡り終えて車道を横断し、細い道に入る。 |
| |
 |
 |
 |
| 突当りの長福寺前の丁字路を右折し、すぐ先の分かれ道は左手に入り、道なりに進む。 |
| |
| いずみ中央公園 |
 |
| 経路案内図 |
| |
| 馬洗いの池 |
 |
 |
 |
| 突当りで道は左に折れる。 |
| 公園入口は、数か所あり左に折れて公園沿いに進むと正門の入口。ここでは右側の階段入口を上る。 |
| 上り切ったら右折しフエンス沿いに進むと、「泉小次郎伝承地 ー馬洗い池ー」白標識と「小次郎池と和泉小次郎」案内板。 |
| この柵に囲まれた池が、小次郎が馬を洗ったと伝えられ「馬洗いの池」で、その昔から一年中水が枯れたことがない、という。 |
| こんな小さな池が、よく水枯れしないのかと思う。そして水源は、どこから? |
| |
 |
 |
 |
| 池の右側を通って道なりに進み、突当りを左折して階段を上り、 |
| 城郭の空堀跡の斜面を登ってゲスト広場手前の道路に出て右折する。 |
|
 |
 |
 |
| ゲスト広場沿い道を進み、園内を半周した辺りに橙色のトイレ(園内唯一のトイレ)。 |
| トイレから道なりに左に曲がり、その先の分かれ道は右手を進んで正面入口広場に出る。 |
| |
|
|
| 広場の外に出て、正門から見た広場と空允秋作の彫刻「門」。 |
|
|
|
 |
 |
 |
| 彫刻「門」の延長上の道を進む。右側に、平成28年に区制30年を記念して植えられた5本のイロハモミジ。 |
| 道はゆるい下り坂となり、分かれ道は右手の階段を下る。 |
| |
 |
 |
 |
| 階段を下りて、「馬洗い池」案内板脇に出て右折し、道なりに進んで、来た時登った階段を下りて、左折する。 |
| |
 |
 |
 |
| 道なりに進んで突当りを右折し、すぐ先の分かれ道は右手に入り、長福寺塀沿いに進む。正面に須賀神社鳥居。 |
| |
 |
 |
 |
| 長福寺:泉小次郎親衛が道場として創建した、伝えられいる。本尊は、釈迦牟尼仏。 |
| 山門。きれに整備された境内に本堂。 |
| 山門を入って左側に、南北朝時代(1336~1392年)の豪族や武士が供養のため建立した板碑。 |
| |
 |
 |
 |
| 山門を出て右折し、突当りに須賀神社鳥居。参道階段を上ったところに小さな社殿。 |
| 須賀神社:泉小次郎親衛がこの地に城を築いた建暦2年(1212年)に、その鎮守神として祀ったのが始りと伝えれている。 |
| 本堂から下方を見ると、相当高いところにあることが分かる。 |
| |
| 神明社へ |
 |
 |
 |
| 参道階段を下りて、山門で右折し、参道を進み、突当りで車道を横断して和泉川沿いの道に出て右折する。 |
| |
 |
 |
 |
| 真っすぐな和泉川沿いの道を進み、公園のバリケード前で右折し、細い道を進む。 |
| なお、バリケード前で左折すると、和泉川にかかるあけぼの橋を渡り、いずみ中央駅北口に通じる。 |
| |
 |
 |
 |
| 突当りを左折し、次の分かれ道も左折して、道なりに進む。 |
| |
 |
 |
 |
| その先の分かれ道を右手を進み、次の分かれ道は左手を、道なりに進む。 |
|
|
|
| 神明社 |
|
|
| すぐ右側の参道階段上に神明社の鳥居と質素で小さな社殿。 |
| 神明社:泉小次郎親衛が城を築いたとき、その鬼門除けとして勧請したと伝えられている。 |
| |
| いずみ中央駅北口へ |
 |
 |
 |
| 参道階段を下りて右折し、突当りで県道22号線「泉区総合庁舎東側」信号に出て左折し、 |
| その先の「泉区総合庁舎前」信号を直進する。信号の右手に、泉区総合庁舎建物。 |
| |
 |
 |
 |
| 信号のすぐ先の、「和泉川・地蔵原の水辺」標識の先で和泉川にかかる「いずみはし」を渡って道路を横断して左折し。 |
| 相鉄線高架沿いに約100mほど進み、横断歩道のところで右折してガード下を潜る。 |
| |
|
|
| すぐ左折したところがハッとするような素敵なエントランス通路、そしていずみ中央駅北口。 |
| |









































































