|
| 2020年7月10日 |
|
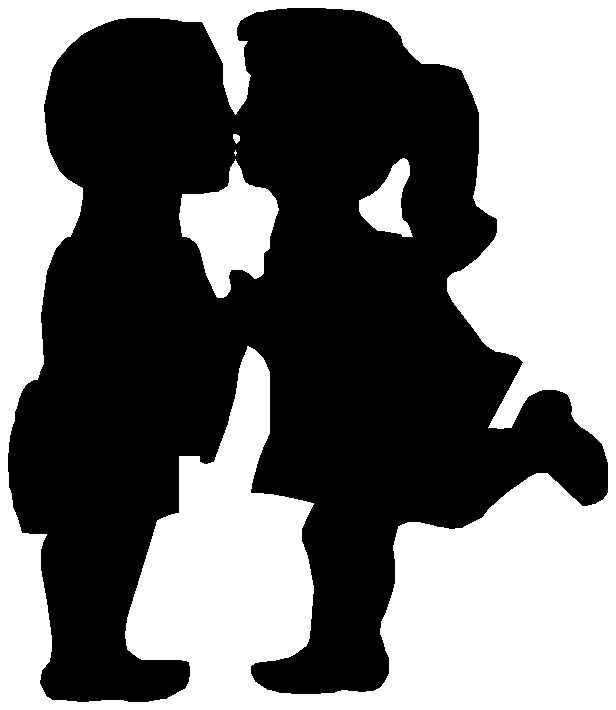 |
一駅読み切り |
|
(神奈川県)相模鉄道沿線・半径1kmの駅
|
|
| |
| 相鉄本線「瀬谷駅」 所在地:横浜市瀬谷区瀬谷4丁目 |
| |
| 開業:1926年(大正15) 一日平均乗降客: 約34,200人(2020年度)、 約44,100人(2019年度) |
| 駅間距離:三ツ境駅から 約1.9km |
| |
| 駅名由来 |
| 地名に由来 |
| 瀬谷という地名は、この地が西側の境川と東側の相沢の間の「狭い谷地」であったことから「狭谷」と呼ばれるようになり、 |
| 「瀬谷」に転じたと言われる。 |
| 史書にその名が登場するのは、室町時代の宝徳年間(1449~52)のことと、いわれる。 |
| 二ツ橋駅 |
| 三ツ境駅と瀬谷駅の間に1927年(昭和2)開業した「二ツ橋駅」があったが、駅間距離が短か過ぎるということで |
| 戦時中の1944年(昭和19)に営業停止し、1960年(昭和35)に廃止されてしまった。 |
| |
| この駅には、6月1日に訪れた。 |
| 瀬谷と言えば「八福神めぐり」巡りが有名であるが、駅から遠いので遠慮して、 |
| 地名由来となった境川」と「相沢川」を訪ねてみた。 |
| 境川:神奈川県北部の城山湖の北、東京都町田市相原町の草戸山(365m)に源を発し、 |
| 藤沢市江の島付近で相模湾に注ぐ、延長約52kmの2級河川。 |
| 境川の名の由来は、武蔵国と相模国の国境とされたことによる。 |
| 相沢川:瀬谷市民の森を源泉として主に瀬谷区内を流れ、境川に合流する延長約5kmの境川水系の河川。 |
| 経路 |
| 瀬谷駅北口→ 瀬谷柏尾道路(瀬谷駅北口前信号)→ 長天寺(横穴古墳跡)→ 相沢川→ 瀬谷柏尾道路→ 瀬谷中学校前信号交差点 |
| → 徳善寺→ 境川→ 瀬谷中学校前信号交差点→ 環状4号線→ 世野(せや)の原鷹見塚→ 瀬谷駅南口 |
| 歩行距離: 約3.4km |
| |
| 瀬谷駅 |
 |
 |
 |
| 橋上駅。改札口、北側昇降口階段。階段側面に「鎌倉古道・北コース」案内板。 |
| 鎌倉古道とは:鎌倉室町時代の「鎌倉上ノ道」、「鎌倉中ノ道」、「鎌倉下ノ道」の総称で、、 |
| 「鎌倉上ノ道」は鎌倉-瀬谷ー信濃(長野)を結ぶ主要道路であった。 |
| 「北コース」:駅北口出発・戻りで、鎌倉古道の13ヵ所の史跡などを訪ねる総延長7.5kmのコースで、所要時間78分。 |
| |
 |
 |
 |
| 北口を出て広場の中の並木通りを進み、突当りで県道401号線瀬谷柏尾道路の「瀬谷駅北口前」信号に出る。 |
| ここでは、相沢川を訪れるため信号を右折するが、後刻この信号へ戻る。 |
| 信号を右折し、瀬谷柏尾道路を道なりに進む。 |
| |
 |
 |
 |
| 「瀬谷小学校前」信号を直進し瀬谷小学校脇坂道を下り、校庭の外れで左折して、坂道を上り右折して広い長天寺境内に入る。 |
| |
|
|
| 長天寺:室町時代の1934年(応永元)大和尚禅師が開山、開基は平本六兵衛。 |
| 明治22年の市町村制公布で、瀬谷村、二ツ橋村、宮沢村が合併し、新たな瀬谷村となった時この長天寺に村役場が置かれた。 |
| 境内の東側にある急な階段を下りて、T字路の車道に出る。 |
| |
 |
 |
 |
| 丁字路を左折し境内沿いに進み、外れで左折し坂道上ったところの小さな祠の脇に、「横穴古墳跡」碑。(祠と碑とは無関係) |
| 横穴古墳跡:1906年(明治39)、当地で農作業中に人骨3体、直刀及び鍔3点、金環2点、琥珀の璽玉3個、鉄轡1個を発掘した。 |
| 出土品から飛鳥時代・白鳳時代(604~708)頃の相当高貴な人の墳墓と推定。現在は、古墳はなく跡碑だけが立っている。 |
| なお、出土品は東京国立博物館に収蔵されている。 |
| 元へ戻り、丁字路を直進すると、約10mほど先で相沢川を渡る。 |
| 当時のことは知らないが、現在は用水路といっていいくらいで、「瀬谷」の地名由来になった川とは想像できない。 |
| 元へ戻り、境川を訪れるため丁字路を右折して境内沿いに進み突当りで県道401号線瀬谷柏尾道路に出て、右折する。。 |
| |
 |
 |
 |
長天寺境内脇坂道を上り、瀬谷柏尾道路を戻ってスタート地点の「瀬谷駅北口前」信号を直進し、
|
| 次の環状4号線との交差点の「瀬谷中学校前」信号も直進する。 |
| |
 |
| なおこの信号交差点を右折すると、 |
| 国道16号線まで一直線に約3km続く通称「海軍道路」で、400本のソメイヨシノの街路樹が並ぶ。 |
| 海軍道路:1943年(昭和18)、旧日本海軍が上瀬谷付近一帯に軍事施設を設置したとき、 |
| 物資輸送を目的に整備された道路が海軍道路の始まり。当時は現在の道路の歩道部分に物資輸送の鉄道線路も敷かれていた。 |
| 終戦後は、この軍事施設はアメリカ軍に接収され昭和40年代後半までアメリカ軍専用道路で、日本人は使用できなかった。 |
| 海軍道路が一般開放され使用できるようになったのは1973年(昭和48)で、 |
| 1978年(昭和53)当時の横浜市道路局により「海軍道路」という愛称がつけられた。 |
| |
 |
 |
 |
| 次の「瀬谷図書館前」信号の分かれ道で瀬谷柏尾道路と分かれ左手を進み、瀬谷図書館前の坂道を下り、 |
| 道なりに左に折れて進み丁字路の出る。 |
| |
|
|
| 丁字路の左手は,立派な山門の徳善寺。 |
德善寺:瀬谷八福神の一つで、毘沙門天を祀っている。1555年(弘治元)創建。
|
| 境内には明治政府の地租改正の増税に対する反対運動の代表として戦い病死した、義民川口平本建功の碑がある。 |
|
|
|
|
|
| 丁字路を右折し道なりに進み、突当りで境川の堤防道に出る。 |
| |
|
 |
|
| 大和市と横浜市(瀬谷区)の境界にある、境川。 |
| 瀬谷の地名由来となった西側の川で、とても品のある川のように見えるが、時には暴れ川になることもあるとは信じられない。 |
| |
 |
 |
 |
瀬谷駅に戻るため今きた道を「瀬谷中学校前」信号迄戻って右折し、
環状4号線を進みその先で4号線と別れ陸橋の側道に入り、相鉄線踏切を渡る。 |
| |
 |
 |
 |
| 踏切のすぐ先の信号交差点を渡った左角に、「世野の原(せやのはら)の鷹見塚」案内板。 |
| 「世野の原の鷹見塚」案内板(要約):慶長年間(1596~1641)、徳川幕府は旗本長田忠勝に上瀬谷をお鷹場支配として与えた。 |
| この鷹貝塚は相模国4郡の鷹狩指揮所の1つとして築かれた。 |
| さらに弟の長田白政は中瀬谷をも支配下におさめ、世野の原に鷹狩り場の大絵巻が繰り広げられた、と言われている。 |
| この鷹狩りは、5代将軍綱吉の「生類あわれみの令」により一時中断したが、幕末まで続けられた。 |
| 信号を左折して道なりに進み、約200m先交差点左手に瀬谷駅南側昇降口階段。 |
| |
































